ジョブ理論とは?デザイナー的な視点から読み解く
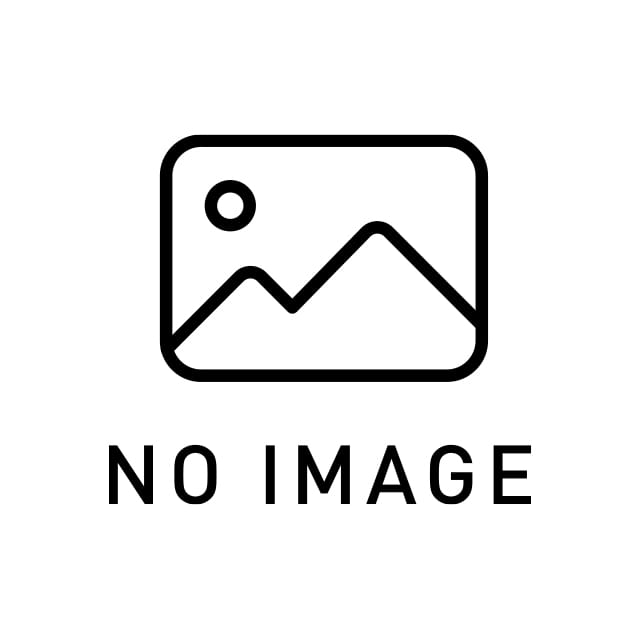
今日は、「ジョブ理論」という少し耳慣れない考え方を、できるだけ日常に近い視点でお話ししてみようと思います。
僕は「マーケティング要素」を踏まえながらデザインを作ってますし、その時、ジョブ理論を想定しながら企画を考えることがあります。
またジョブ理論を知っておくと、「なんでこれを選んだんだろう?」という日常のモヤモヤを、少しだけ言葉にしやすくなります。
一見すると複雑に感じられる理論ですが、実は私たちの日常に深く関係しています。今回はそれをなるべくわかりやすく、丁寧にお伝えします。
目次
「ジョブ」とは何か?――進歩への雇用
ジョブ理論の基本的な考え方は、「人は何かを“したい”ときに商品やサービスを“雇用する”」というものです。ここでいう“ジョブ”とは、特定の状況で人が達成したい進歩のことを指します。
たとえば、ある人がミルクシェイクを朝に買う理由が「空腹を満たす」ことだけではなく、「長時間の通勤を少しでも楽しいものにしたい」だったとします。
その瞬間、ミルクシェイクは飲み物という存在ではなくなり、通勤時間を快適にする“ツール”として雇用されているわけです。
ジョブ理論で大切な4つのこと
「ジョブ」とは、欲求ではなく“進歩”である
ジョブ理論では、顧客が商品やサービスを選ぶ行為を「雇用する」と表現します。
この“雇用”の対象となるのが、「進歩を遂げたい」という人間の根源的な動機です。
ここで言う“進歩”とは、問題を解決したい、望ましい未来に近づきたい、という願いそのものです。
それは「何かを便利にしたい」という機能的な側面だけではなく、「周囲の期待に応えたい」「自分を認めてほしい」といった社会的・感情的な文脈も含んでいます。
重要なのは、商品やサービスが担う“役割”が、この進歩と直結しているかどうかです。
ジョブ理論の根本には、「状況の読み解き」があります。
人は同じ商品でも、置かれた状況によって求める意味合いが異なるからです。
P&Gのおむつの事例は象徴的です。ただ安価で吸収性が高いという機能性だけではなく、「赤ちゃんがぐっすり眠れることで親の生活にゆとりが生まれる」「夫婦の時間が取れる」という社会的・感情的な価値が評価されました。
つまり、ある商品が選ばれる背景には、「この状況だからこそ、その商品が必要だ」というコンテクストがあるのです。
製品に価値はない!
僕たちはしばしば、「この商品は価値がある」「あのサービスは素晴らしい」といった表現を使います。
でもそれは本当に“商品自体”に価値が宿っているのか?ジョブ理論の考え方に立脚すれば、その答えは明確に「No」といえます。
価値とは、製品そのものに備わっているものではなく、顧客がそれに“見いだす”ものにすぎないのです。この視点を端的に表すのが、「価値とは、WHO(顧客)が WHAT(プロダクト)に見いだした便益と独自性である」という定義です。
つまり、どんなに高性能で、画期的で、魅力的な製品であったとしても、それが誰にとっても価値がある”わけではないのです。ある顧客にとっては役に立つが、別の顧客には無意味かもしれない。
つまり、価値の有無は、常に顧客の主観に委ねられているというのが本質です。
ジョブは「機能+感情+社会性」がセット
ジョブとは単に機能的な問題解決にとどまらず、感情的・社会的な側面をあわせ持つということです。多くの人は「便利だから」「使いやすいから」という理由だけで商品を選んでいるように見えるかもしれません。
しかし実際には、「安心したい」「認められたい」「誇りを持ちたい」といった感情的・社会的な期待が裏にあります。たとえば住宅の外構工事では、単に車が止められるスペースが欲しいのではなく、「家族との時間を豊かにしたい」「来客に恥ずかしくない外観にしたい」といった気持ちが動機となっていることが多いのです。
これだけは覚えよう
- 単に「便利だから」ではなく、
- 機能的欲求(ラクになる、時短できる)
- 感情的欲求(安心したい、満足したい)
- 社会的欲求(よく見られたい、評価されたい)
- これらを満たすために、商品は“雇われる”
同じ人でも、状況が違えば求める意味も変わる
例えば朝のマックミルクシェイクを買う場合。
なにも考えなければ空腹を満たすものと感じるかもしれませんが、実は「通勤が退屈だからそれを飲みながら運転したいという「楽しさ」への雇用かもしれません。
ジョブ理論では、「何を買うか」ではなく、「なぜそれを“雇う”必要があったのか?」という文脈に注目します。
そしてジョブは「誰が」や「年齢がいくつか」といった属性ではなく、「その人がどんな状況に置かれているか」によって成立し、「なぜその瞬間にそれを選んだのか」が大切になります。つまり、同じ人でも、置かれた状況によって“雇う対象”は変わるということです。
この機能すごくない!?は正しい?
ジョブ理論で大切なのは、便益と独自性は「自分ごと化」されたときにはじめて価値になるという点です。
企業のなかには「業界初のトライバンドWi-Fi 6Eによる高速・安定通信!」や「他社製品にはない、エネルギー消費量のリアルタイム可視化機能。」など「うちの商品は、これだけ便利で、他にない機能を持っています」と誇らしげにアピールしているケースがあります。
しかし、顧客がその特徴に対して「自分の課題がこれで解決する」「これはまさに今の私に必要なものだ」と納得しなければ、それは“価値”ではなく、ただの“機能の列挙”に終わってしまいます。
言い換えれば、「WHAT(プロダクト)」がいくら優れた便益や独自性を持っていても、それを「WHO(顧客)」が“自分にとっての意味”として認識しなければ、そこには価値は生まれないのです。どれだけ尖った機能を持っていても、それが顧客の生活や状況、期待に関わりがなければ、商品は「選ばれない」「雇われない」ということになります。
この考え方を突き詰めると、プロダクトはそれ自体に価値を持たないという結論に行き着きます。
プロダクトはあくまで、「価値になるかもしれない便益や独自性を“提案している”状態」にすぎません。真の価値は、その提案を受け取った顧客が、自らの文脈において意味づけしたときにのみ生まれる。つまり、価値の創造者は企業ではなく、常に顧客なのです。
■ たとえば、身近な日常で見つかる“ジョブ”の例
ここまでジョブ理論について説明しましたが、正直、ピンと来ていない人もいるはず。そのため、生活の中にある「ジョブ」をピックアップしてみました。
身近な日常には、たくさんの「ジョブ(成し遂げたい進歩)」が潜んでいます。普段何気なく行っている行動の裏には、「こうなりたい」「これを解決したい」という欲求が隠れています。
| 片付けるべきジョブ | シーン | 雇用されるもの |
|---|---|---|
| 退屈な通勤時間を有意義に過ごしたい | 満員電車の中で、座ることもできない | 音楽配信サービス (好きなアーティストの新曲を聴いて気分転換)、ポッドキャスト (興味のあるニュースやトーク番組で知識をインプット)、オーディオブック (小説を聴いて物語の世界に浸る)、電子書籍リーダー (片手で手軽に読書を楽しむ) |
| 一人で気軽に、美味しいコーヒーを飲んでリラックスしたい | 仕事の合間の休憩時間。 仕事前の朝の時間に、少しでも自分の時間を持ちたい。 | 個包装のドリップコーヒー (手軽に本格的な味わい)、コーヒーメーカー (自宅で手軽に淹れたてを味わう)、カフェのテイクアウト |
| 忙しい毎日でも、部屋をきれいに保ちたい | 平日は仕事で掃除の時間が取れない。週末にまとめて掃除をするのは大変。 | ロボット掃除機 (留守中に自動で掃除してくれる)、お掃除シート (気づいたときにサッと拭ける)、ハウスクリーニングサービス |
| スキルアップのために、空いた時間を有効活用したい | 通勤時間や寝る前の少しの時間を使って、何か新しいことを学びたい。 | オンライン学習プラットフォーム (様々な分野の講座を受講)、語学学習アプリ (ゲーム感覚で外国語を習得)、ビジネス書 |
| 手軽に、でも栄養バランスの取れた食事を済ませたい | 仕事で疲れて帰宅し、すぐに食事の準備をするのが面倒。でも、コンビニ弁当ばかりでは栄養が偏るのが心配。 | カット野菜 (すぐに調理に取り掛かれる)、冷凍食品 (レンジで温めるだけで済む)、ミールキット (必要な食材とレシピがセットになっている)、宅配弁当サービス (栄養バランスの整った食事が自宅に届く) |
■ なぜジョブ理論がデザイナーにとって重要なのか?
デザイナーにとって作るものは、数ある選択肢の中からお客様に「選ばれる」必要がありますよね。お客様が他の商品ではなく、私たちの商品を優先的に「引き入れる」のはなぜでしょうか?
それは、単に見た目が良いとか、機能が優れているだけではないはずです。お客様が抱える「こうなりたい」「これを解決したい」という欲求に対して、私たちのデザインが、他のどんな選択肢よりも明確に応えられているからです。
ジョブ理論の観点から考えた場合、デザインの役割は下記のようになり、かっこいい・美しいよりも目指すべき方向性になってくるのです。
- 顧客の「困った」に、ど真ん中で応えるデザイン: お客様が本当に解決したい問題、達成したい目標を深く理解し、その核心に刺さる機能や体験をデザインできているか?
- 私たちの「らしさ」が、お客様にとっての「特別」になるデザイン: 競合には真似できない、独自のアイデア、技術、ブランドイメージが、お客様にとって他に代えられない価値になっているか?
- 「欲しい!」の気持ちに火をつけるデザイン: 機能的な価値はもちろん、使っていて気持ちが良い、所有欲を満たす、誰かに見せたくなるような、感情に訴えかけるデザインになっているか?
- スムーズに「手に入る」体験のデザイン: お客様が欲しいと思った時に、ストレスなく情報を得て、購入し、使える状態になるまでの体験全体がデザインされているか?
デザインをする時、目の前のモノだけを見ていませんか?
デザインの良し悪しは、かっこいいデザイン・おしゃれなデザインで成り立つのではなく、「使う人・見る人が、どんな状況で、何を達成したいのか」を踏まえてこそ成立します。
つまり客様がその商品を使う「特定の状況」や「背景」を深く理解することが、本当に価値のあるデザインを生み出す鍵となります。ジョブ理論を知ると、「かっこいいからこの色にした」ではなく、「ユーザーが安心感を求めているからこのトーンにした」といった意味のある選択ができます。
- お客様の「日常」を想像するデザイン: お客様はどんな場所で、どんな時に、どんな目的で私たちの商品を使うのでしょうか?その時の感情や周りの状況はどうでしょうか?
- 時間軸で考えるデザイン: 購入前から、使用中、そして使い終わった後まで、お客様の体験はどのように変化していくでしょうか?各段階で何が重要になるでしょうか?
- 「誰にとって」のデザインか?: 同じ商品でも、使う人によってニーズや感じ方は異なります。ターゲットとなるお客様の属性やライフスタイルを深く理解していますか?
- 「なぜそれを使うのか?」を問い続けるデザイン: お客様は表面的な機能だけでなく、その奥にあるどんな欲求を満たしたいのでしょうか?
クライアントやチームに“意図”を説明できる
従来の「なんとなく良さそう」「見た目が美しいから」といった主観的な説明では、相手を十分に説得することは難しいです。
しかし、ジョブ理論を用いることで、デザインの背後にあるユーザーの具体的な状況、心理状態、そして達成したい進歩という客観的な根拠を示すことができるようになります。
「このタイミングのユーザーは、こういう心理状態だから、こういう導線にしている」 と説明できるようになります。
ECサイトの設計
ECサイトの商品一覧ページやカテゴリページは、顧客が商品を探し、比較検討するための重要なページです。ランディングした顧客は、それぞれの目的を持っており、私たちはそれらの『見つけたい』『知りたい』『選びたい』 というジョブを最大限にサポートする必要があります。
デザイン提案
- 検索機能と絞り込み機能の強化: 目的の商品が明確な顧客のために、キーワード検索はもちろん、カテゴリ、価格帯、ブランド、サイズ、カラー、レビュー評価など、詳細な条件で絞り込める機能を分かりやすく配置します。これにより、『目的の商品へ最短距離でたどり着きたい』 ジョブを支援します。
- 並び替えオプションの提供: 「おすすめ順」「価格の安い順」「価格の高い順」「新着順」「レビュー評価の高い順」など、顧客が自分の重視する要素で商品を並び替えられるようにします。『効率的に比較検討したい』『お得な商品を見つけたい』『最新の商品をチェックしたい』 といった多様なジョブに対応します。
- 注目商品のピックアップと表示: 新着商品、セール商品、ランキング上位商品、おすすめ商品などを目立つ場所に表示します。まだ具体的な目的がない顧客に対して、『魅力的な商品を発見するきっかけを提供したい』『トレンドを知りたい』『お得な買い物をしたい』 というジョブを刺激します。
- 商品のサムネイルと基本情報の充実: 商品画像は魅力的で分かりやすいものを掲載し、商品名、価格、簡単な説明、レビュー評価などを一覧で確認できるようにします。これにより、『効率的に商品の概要を把握し、比較検討のをスムーズに進めたい』 ジョブを支援します。
- レビューの可視化: 商品一覧やカテゴリページでも、レビュー評価の星を表示したり、件数を表示したりすることで、顧客は商品の評判を直感的に把握できます。
- 関連商品の提案: 商品一覧の下部やサイドバーなどに、閲覧履歴やカートに入れた商品、または類似カテゴリの商品などを表示することで、『もしかしたらこれも必要かも』『他の選択肢も見てみたい』 という潜在的なジョブを喚起します。
■ その他、たとえばこんな違いが出ます
下記の項目をみてもらうとわかると思いますが、説明できるデザイナーはあらゆることも「機能的に」伝えるのではなく、「なぜこれが必要か」「どのような状況で使われるのか」を考えながらデザインしています。
| 項目 | ジョブ理論を知らないデザインの考えること | ジョブ理論を知っているデザイナーの考えること |
| 【ターゲット理解】 | 年齢、性別、興味関心などの表面的な属性で捉える | ユーザーが「どんな状況で」「何を成し遂げたいのか」という深層心理に基づいて捉える |
| 【配色】 | トレンドの配色で、かっこよく見えるバナーを制作 | 「ユーザーは今“安心したい”」という文脈を意識し、柔らかく丁寧な配色・文言に |
| 【情報設計】 | 提供したい情報を一方的に整理する | ユーザーが「知りたいタイミングで」「必要な情報にアクセスしやすい」流れを設計する。情報の優先順位はユーザーのジョブ達成度合いで決める |
| 【画像・動画の活用】 | 商品やサービスのイメージを伝える素材を感覚的に選ぶ | ユーザーが「購入後の生活を具体的にイメージしたい」「抱える課題が解決される様子を見たい」というジョブに基づき、感情に訴えかけるストーリー性のある素材を選ぶ |
| 【サービスページ】 | サービス紹介ページに「機能」だけを並べる | 「この商品を使う人は“周囲からの評価”を気にしている」から、ビフォーアフターで生活変化を視覚化 |
| 【CTA】 | CTAボタンは右下に置くのが“なんとなく”正解 | 「迷っている人の背中を押したい」から、CTAはユーザーの視線導線上に配置+言葉も“感情に寄り添う表現”に |



