化粧水パッケージデザインで大切にしたい、7つの視点
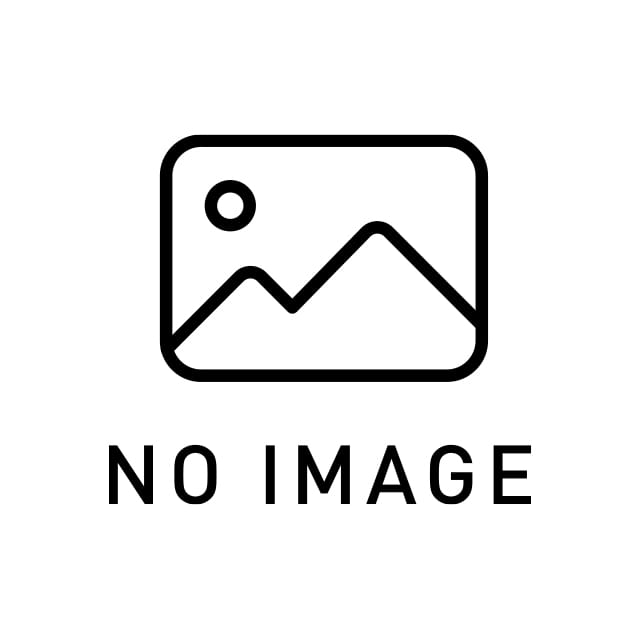
目次
はじめに
化粧水のパッケージデザインでは、「誰に、どんな便益を、どんな場面で届けるか」を明確にし、その本質を言葉とビジュアルで一貫して伝えることが大切です。ただ美しくするのではなく、選ばれる理由が“ひと目で伝わる”設計を意識すること。つまり、「そもそもこれって何?」と、商品やサービスの“根っこ”をとことん掘り下げて考える姿勢が、デザインの出発点になります。
例えばですが、化粧水のパッケージデザインを依頼されたとき、あなたなら何から始めますか?
多くの人は、まずこう考えるかもしれません。
- 化粧品の参考事例を探す
- どんな見た目が「キレイ」に見えるか調べる
- 色やフォント、ラベルの雰囲気を考える
もちろんそれも大切ですが、僕はまず「中身をとことん調べること」から始めます。なぜなら、化粧水と一口にいっても、敏感肌向け、エイジングケア、導入美容液タイプなど中身はさまざま。それがわからなければ、誰にどう伝えるべきかも決められません。本質を知らずして、意味あるデザインは生まれないのです。
| 商品の特徴 | 向いているデザインの方向性 |
|---|---|
| 敏感肌用 → 成分がシンプルで無香料 | 清潔感・やさしさ・信頼感 |
| エイジングケア用 → 高機能・高価格 | 高級感・信頼性・専門感 |
| 10代向け → 香りやパッケージ重視 | ポップ・かわいい・親しみやすさ |
その製品の特徴によっては、ただ「キレイに見せる」ではなく、「敏感肌の女性が、安心して手に取れること」が本質かもしれませんよね。そうなると、「安心感のある色」「肌にやさしいイメージ」「成分のやさしさが伝わる言葉づかい」が必要になるわけです。
要は見た目の話は、あくまで“最後”です。
化粧水のパッケージデザインで意識すべき7つのポイント
ここでは、僕が実際に化粧水のパッケージデザインを依頼されたと仮定して、必ず確認することを列挙しておきます。
ちなみに僕の肌感覚としてこれらをちゃんと調べているデザイナーはめちゃくちゃ少ない印象です。僕は制作畑なのですが、多くのデザイナーは「意匠をどうするか?」ということばかり考えています。
だからとても初歩的なことをお伝えするのですが、この当たり前を必ず心がけてもらいたいです。
①ターゲット(誰に向けてつくられた?年齢・性別・悩み)
パッケージデザインを始める前に最も重要なのが、「この商品は誰のために作られたのか?」を見極めることです。年齢や性別だけでなく、その人がどんな悩みを持ち、どんな状況でこの商品を必要としているのかまで想像していくことで、伝えるべき雰囲気やメッセージが明確になります。たとえば、敏感肌の20代女性と、エイジングケアを求める40代女性では、求める印象がまったく異なります。
その人が商品棚の前でどんな気持ちで立っているか、どんな言葉に安心したり、どんなデザインに惹かれたりするのかを想像することが、トーン設計の第一歩です。親しみやすさ、清潔感、高級感といった「空気」を正しく届けるためにも、デザインはまず“相手の感情”から始めましょう。
ターゲットは、商品開発時にしっかり考えられていることが多いため、クライアントに直接聞いてしまうのが一番です。
- 一番使ってほしいのは、どんな人ですか?(性別・年代・職業など)
- その人はどんな肌の悩みを持っていると思いますか?
- なぜこの商品を使おうと思うのか? きっかけやシーンはありますか?
このように聞くことで、伝えるべき“言葉や空気感”が見えてきます。ターゲットを知らないままデザインするのは、暗闇で矢を放つようなものです。
【その他調べ方】
- 公式サイトやパンフレットにある「ターゲット像」や「ブランドストーリー」
- SNS広告やインフルエンサー起用の傾向(誰に訴求している?)
- 商品レビューに出てくる年齢・性別・悩み(実際の利用者)
②ベネフィット(商品が持つ“便益”を言語化しておく)
デザインは商品の特徴を伝えるものではなく、「それを使ったらどうなるか」という体験やベネフィット(便益)を視覚的に届けるものです。たとえば「保湿成分たっぷり」よりも、「朝から夕方までうるおいが続く」ことの方が、ユーザーの実感に近く、響きやすい情報になります。だからこそ、“変化”を想像しながらデザインを考えることが重要です。
「しっとり落ち着く肌感」「リセットされるような香り」など、使った後に得られる嬉しい気持ちを言葉にしてみることで、パッケージの色、質感、書体の選び方が見えてきます。特徴を並べるのではなく、使った人の未来を表現することが、ベネフィットベースのデザインです。
※ベネフィットは特徴ではなく“使った後の嬉しさ”を表現する
- 使った人が「どんな体験を得られるか?」を理解する
- 「一日中うるおいが続く」→やわらかくしっとりした印象の色や質感に
③商品が“雇われる理由”(Jobs)を見つけておく
「なぜこの商品が手に取られるのか?」を掘り下げることで、デザインの方向性はぐっと明確になります。これは“Jobs to Be Done”という考え方で、ユーザーが何らかの状況で「この商品を雇う=選ぶ」理由を探る手法です。たとえば「朝の忙しい時間に、ワンステップで肌を整えたい」なら、直感的に機能が伝わるシンプルなデザインが効果的です。
パッケージは、店頭やEC画面の中で“瞬時に選ばれる理由”を伝える装置です。そのためには、ユーザーがどんな文脈・気持ちで商品を選んでいるのかをつかむことが不可欠です。価格、タイミング、期待感といった背景をデザインに反映することで、「自分のための商品だ」と感じてもらえるようになります。
④ブランドの考え方(ナチュラル志向?ラグジュアリー?)
ブランドがどんな世界観や価値観を大切にしているのかを知ることは、デザインの方向性を決めるうえで非常に重要です。デザインがブランドの空気とズレてしまえば、せっかくの商品も伝わりません。
ブランドが「ナチュラル志向」なら、やさしく落ち着いた色味や質感。「サイエンス志向」なら、精密さや機能性を感じさせるデザインが求められます。一貫した世界観は、ユーザーに安心感と信頼を与えます。
デザインを考える際は、まずはブランドのウェブサイトやパンフレット、他の商品をよく観察してみましょう。どんな言葉づかいをしているか、他の商品と並べて違和感がないかを意識して見ます。
その上で、「この商品はブランドの中でどんな役割なのか?」をクライアントに尋ね、一貫性を保った表現を組み立てます。
【質問例】
- このブランドが大事にしている世界観や価値観は?
- ほかの商品と見た目や雰囲気を揃える必要がありますか?
- ブランドの中で、この化粧水はどんな位置づけですか?
⑤価格帯・販売場所(ドラッグストア?百貨店?ネット通販?)
化粧水の価格や販売場所は、パッケージデザインに大きく影響します。
たとえば、ドラッグストアで千円台の商品であれば、親しみやすさや手に取りやすさが求められますよね。一方で、百貨店やラグジュアリーECサイトで展開される場合はどうでしょう。高価格帯の商品なら、上質感や特別感、信頼性の演出が欠かせませんよね。
つまり、価格と販売チャネルによって、色や素材、タイポグラフィの使い方まで変わってきます。販売チャネルとは「このデザインが実際に人に出会う状況」をシミュレーションすることです。ECサイトで販売するなら、写真越しに伝わる質感や構図、文字の視認性を重視すべきですし、店頭販売なら棚の中で埋もれずに目立つ工夫が必要です。
このように、デザイナーとしては、商品の“売られる場面”を具体的にイメージして設計することが重要です。
【check!】
クライアントには「販売予定価格」「販路(店頭か通販か)」「主な競合」などを事前に確認しましょう。文脈に合ったデザインが、選ばれる理由になります。
⑥競合との違い(似ている商品との差別化ポイントは?)
最後に欠かせないのが、「他の似た商品とどう違うのか?」という視点です。世の中にはたくさんの化粧水があります。その中でなぜこの商品が選ばれるべきなのか、どんな“違い”や“強み”があるのかを知らなければ、他と似たような表現になってしまいます。デザインの仕事とは、「その商品が、なぜ特別なのか」を視覚で語ることでもあります。
調査としては、近い価格帯や用途の化粧水をいくつか比べてみるのがおすすめです。レビューやパッケージを見比べて、差別化ポイントを見つけましょう。クライアントには、「競合として意識しているブランドはありますか?」「この商品の一番の強みは何ですか?」と質問してみてください。その答えが、コピーやキービジュアルの“核”になります。
「本質」を掴みましょう。
デザインをするとき、僕はいつも「この商品やサービスの本質って何だろう?」と自分に問いかけます。本質とは、ただの特徴やスペックではなく、その存在理由や、誰のどんな悩みをどう解決するのかという“根っこ”の部分です。見た目が整っていても、そこが見えていなければ、相手の心には届きません。きれいなだけではなく、「なんかこれ、私にぴったり」と感じてもらえるためには、その人に響く“伝え方”ができていなければならないのです。
ただし、その「本質」は最初から明確に用意されているものではありません。「この商品の本質は何ですか?」とクライアントに聞いても、すぐに答えが返ってくることは少ないです。だからこそ、調査やヒアリングを重ね、いろんな角度から観察し、自分自身で“発見していく姿勢”が必要です。そして、見つけたその本質を、どうすれば一目で伝わる形にできるかを考える──それこそが、デザインの役割であり、プロジェクトの核心だと僕は思っています。



