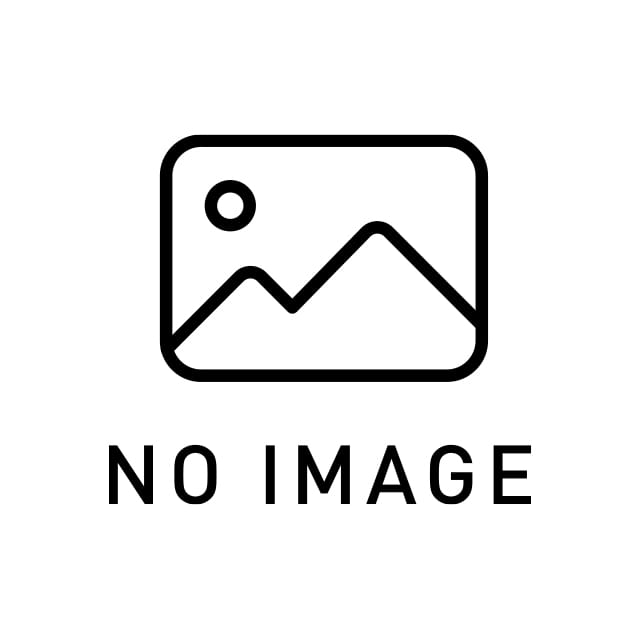「コンセプチュアル」とはなにか?具体例で考えてみる

ブランディングの世界には数多くの理論や手法がありますが、その中でも実務に直結する考え方を体系的にまとめた本のひとつに『ブランディングの教科書』があります。著者は、日々のデザイン業務において常に意識している8つの視点を挙げています。
- 差異化できているか
- シンプルであるか
- コンセプチュアルか
- 構造化されているか
- テイストがあっているか
- メジャー感があるか
- ディテールの完成度が高いか
- 美意識があるか
どれもブランディングデザインを磨く上で欠かせない要素ですが、今回はその中から特に「コンセプチュアル」という項目にフォーカスしてみたいと思います。
「コンセプチュアル」という言葉は、現場でよく使われるものの、いざ説明しようとすると意外と難しいものです。この記事では、この「コンセプチュアル」という考え方を初心者でも理解できるように分解し、実際に使えるヒントや事例を交えながら解説していきます。
目次
そもそも「コンセプチュアル」とは?
僕が考えるコンセプチュアルとは、ブランドやプロジェクトの「何を伝えたいのか」という意味を出発点にし、その意味を形や色、言葉、ふるまいに変換することです。
単に見た目がかっこいい、流行っているからといった理由でデザイン要素を決めるのではなく、「何を伝えたいか?」という中心的な考え(コンセプト)を土台にして、すべての表現を組み立てます。
例えば、「速さ」を伝えたい場合、斜めのラインや軽い色を使うことで、見る人が無意識に速さを連想できるようにします。こうして作られたデザインは、「なぜこの形なのか?」「なぜこの色なのか?」という質問にすべて答えられる状態になっています。そして、その答えがブランドや商品の一番大切な価値としっかり結びついています。
コンセプチュアルなデザインは、単なるビジュアルの魅力ではなく、“意味を持ったビジュアル”です。
そもそも、シンプルであることが大事!
シンプルなデザインは、ブランドメッセージを正確かつ強く伝えるための重要な要素です。意味がシンプルであれば、それを表現する形も自然と力強くなり、情報伝達力は飛躍的に高まります。これは、いわば「伝言ゲーム」を加速させる仕組みです。
しかし、多くの人が誤解しているのが、シンプル=形が単純という考え方。形だけをミニマルにしても、デザインの意味が曖昧であれば本末転倒です。本当に大切なのは「意味のシンプルさ」。意味が研ぎ澄まされていれば、形が複雑でも構いません。逆に、どれほど造形をそぎ落としても、メッセージがぼやけていれば効果は半減します。
シンプルなデザインとは、見た目の話ではなく「伝えるべきことを一点に絞り込んだ状態」のことなのです。
シンプル→コンセプチュアルという流れ
「シンプルであること」と「コンセプチュアルか」は切り離せません。意味を一点に絞り込み、それをコンセプトとして形にする。意味をシンプルに表現するということは、そのままコンセプトを具現化することです。
ブランドコンセプトを的確に形に落とし込めれば、それは単なる装飾ではなくブランドの旗印となり、デザインそのものがビジネスのメッセージになります。
『ブランディングの教科書』でも紹介されていますが、例えば、エイトブランディングデザインの「輪違い」のロゴ。一度その意味と造形をセットで理解すれば、「共創」というブランドメッセージがロゴを見るたびに自然と想起されます。そして、その意味を覚えた人が他の誰かに伝えれば、メッセージは広がり、出会いが生まれ、ビジネスは成長していきます。
コンセプトを形にすることは、ブランドの物語を広めるための最も強い手段なのです。
なぜコンセプチュアルが大事なのか?
僕が考えるコンセプチュアルなデザインのメリットは、大きく分けて8つあります。
1. 他と被らない(差別化)
流行のデザインはすぐに真似されてしまいます。しかし、意味や考え方から生まれたデザインは、形だけをコピーしても本質を再現できないため、簡単に模倣されません。
2. 迷わない(意思決定の基準)
複数のデザイン案があるときでも、「どちらがコンセプトに合っているか」という基準で判断できます。好みの対立ではなく、論理的に選べます。
3. チームで再現できる(再現性)
制作メンバーや外注が変わっても、コンセプトという共通の軸があれば、トーンや方向性がバラバラになるのを防げます。
4. 覚えてもらえる(記憶定着)
デザインの裏にあるストーリーや意味を知ると、ただ見た目が良いだけのものより深く印象に残り、忘れられにくくなります。
5. どこでも使える(拡張性)
新しい商品やサービスが増えても、核となるコンセプトがあるため、ブレずに展開できます。
6. 説明できる(説明責任)
クライアントや上司にデザインの意図を問われても、明確な理由を伝えられるため、納得を得やすくなります。
7. ブランドの信頼を高める
意味に基づくデザインは、顧客に「このブランドは一貫している」と感じさせ、信頼感を醸成します。
8. 長く使える(持続性)
形の流行は数年で変わりますが、意味の核は長く使えます。結果的にブランド資産として積み上がります。
コンセプチュアルを生み出すための思考法
コンセプチュアルなデザインを作るための最初のステップは、そのデザインで一番伝えたいことを短く、はっきりした一文にまとめることです。
僕はこれを「コンセプト文」と呼びます。抽象的すぎず、具体的すぎず、ブランドや商品の価値を的確に表す一文が理想です。
たとえば、「雨の日を、好きな日に変える。」というコンセプト文を考えてみましょう。この場合、雨の日のネガティブな状況をポジティブに転換する楽しさや、柔らかな雰囲気がテーマとして浮かび上がります。色使いでは、曇り空を連想させるグレーやネイビーを基調にしながら、晴れ間の希望を感じさせるようなイエローやライトブルーを差し色として加えることで、コンセプトを表現できます。写真には、憂鬱な雨の日の風景ではなく、水たまりに映る空や、窓についた雨粒を美しく捉えたものを選ぶと良いでしょう。フォントも、柔らかい曲線を持つものや、手書き感のあるものを選び、温かみのある印象を与えます。
もう一つ、「ひと口で、旅に出る。」というコンセプト文もあります。これは、ただ食事をするのではなく、食べた瞬間に遠くの国や土地の情景が広がるような体験をテーマにしたものです。味覚を通して旅をする喜びを提供するブランドのイメージです。色使いでは、旅先の異国の風景を思わせる、鮮やかでエキゾチックな色合いを取り入れます。写真も、料理そのものだけでなく、その料理が生まれた土地の風景や文化を感じさせるものを添えると効果的です。チラシやWebサイトでは、旅のしおりや地図を連想させるような遊び心のあるレイアウトにすることも可能です。
このように、「意味」を「形」に結びつけることが、コンセプチュアルなデザインの基本です。コンセプト文という核があることで、デザインの各要素に説得力のある「理由」が生まれ、見る人に一貫した世界観を伝えることができます。
見た目以外も合わせていく
さらに重要なのは、見た目以外の要素も含めて考えることです。言葉遣いやもしリアルサービスなら接客態度も。またSNSの投稿内容までコンセプトに合わせることで、ブランド全体が一つの世界観で統一されます。
ズレやギャップを探す
世の中の「常識」と、顧客の「本音」の間にあるズレを探すのも有効な方法です。このギャップを解決することが、コンセプトになることもあります。 例: 「高級家具は高くて手が出せない」という常識に対し、「安くて自分で組み立てられる」というIKEAのコンセプトが生まれました。
また、コンセプト作りには「ズレやギャップ」を探すという手法も有効です。世の中の常識と顧客の本音の間にある違和感を見つけ、それを解決する形でコンセプトを設定します。例えば、「高級家具は高くて手が出せない」という常識に対し、IKEAは「安くて自分で組み立てられる」という新しい価値を提示しました。このように、ギャップから新しい発想が生まれることも多いのです。
制約を活かす
制約を活かすという考え方も大切です。使える色や素材、印刷方法に制限がある場合、それを逆にブランドの特徴として前面に出すことで、個性として成立させられます。
コンセプトの種を見つける方法
強いコンセプトを作るためには、企業や商品の中から「コンセプトの種」を見つける必要があります。種となるのは、他社にはない歴史や製法などの唯一性、顧客が求める本当の目的(何を買うかではなく、なぜ買うのか)、業界と生活者のズレ、実績や数字などの裏付け、使う言葉や禁止事項といった世界観のルール、そしてそのブランドらしい行動のパターンです。これらを掘り起こし、言葉にして整理することで、コンセプトは明確になります。
- 7秒以内で説明できるか
- 逆にしたら成立しないか
- ロゴを隠してもブランドが想起できるか
- 言葉だけでなく裏付けがあるか
- 新しい施策をしてもブレないか
- 競合が真似すると嘘っぽく見えるか
- チーム内で再現できるか
コンセプチュアルかどうかを見極める基準
完成したデザインが本当にコンセプチュアルかどうかは、いくつかの基準で判断できます。まず、7秒以内で説明できるかどうか。長く説明しないと伝わらないコンセプトは、現場で使いづらくなります。次に、逆のことを言ったときに成立しないかどうかを確かめます。「おいしい健康食」というコンセプトなら「まずい健康食」は成り立たないので、独自性があると判断できます。
また、ロゴを隠しても色やレイアウトだけでブランドを想起できるかどうか、言葉だけでなく証拠が伴っているかどうか、新しい取り組みをしても軸がぶれないかどうか、競合が真似したときに不自然に見えるかどうか、そしてチーム内の別のメンバーが作っても同じ方向性の案になるかどうかも重要なポイントです。
7秒以内で説明できるか
逆にしたら成立しないか
ロゴを隠してもブランドが想起できるか
言葉だけでなく裏付けがあるか
新しい施策をしてもブレないか
競合が真似すると嘘っぽく見えるか
チーム内で再現できるか
おわりに
コンセプチュアルなデザインとは、意味を起点に形やふるまいを設計することです。それは単なる装飾ではなく、ブランドの本質を表現する強力な手段です。今日からは、まず「意味を一文にまとめる」ことから始めてみましょう。そこから、あなたのデザインはただの見た目の良さを超えて、「語れるデザイン」に進化していきます。