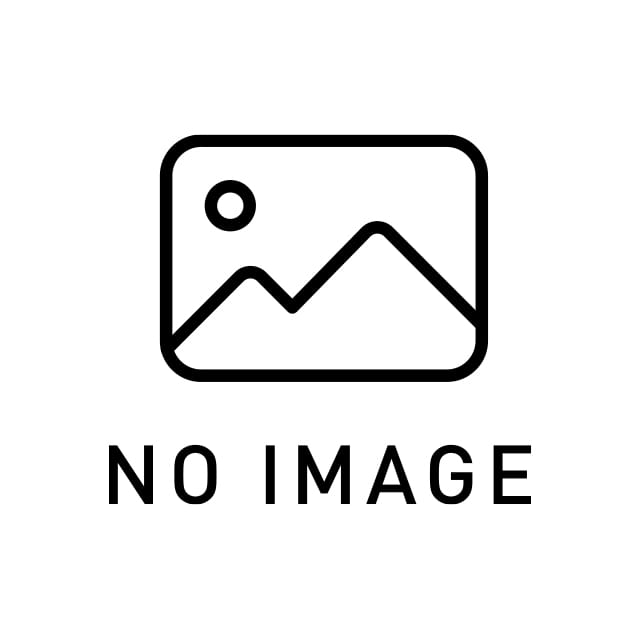ブランドロイヤリティとは?ブランディング初心者でもわかりやすく紹介!

こんにちは!今日はブランドロイヤリティについて、みなさんと一緒に考えていきたいと思います。
クライアントから「もっとファンを増やしたい」「リピーターを作りたい」という相談を受けることはありませんか?実は、これはブランドロイヤリティの本質に関わる重要なテーマなんです。
今、私たちの周りには無数のブランドが存在します。その中で、なぜか「これじゃないと!」と思えるブランドがありますよね。たとえば…
「このブランドのスニーカーは、デザインも履き心地も最高だから、新作が出るたびにチェックしちゃう」
「このカフェに来ると、店内の雰囲気もスタッフの対応も心地よくて、つい長居してしまう」
「このブランドは環境への取り組みが素晴らしくて、少し価格が高くても応援したくなる」
これらは、すべてブランドロイヤリティの表れです。でも考えてみてください。単に「いつも使っているから」という習慣的な購入と、「このブランドが好きだから」という深い愛着は、まったく異なるものですよね。
実は、ブランドロイヤリティは、デザイナーが作り出す「体験」と密接に関係しています。製品やサービスの見た目だけでなく、それを使う人の気持ち、生活との関わり、そして価値観との共鳴…。これらすべてが、強いブランドロイヤリティを生み出す要素となるのです。
今回は、このブランドロイヤリティについて、その本質から実践的なアプローチまで、デザイナーの視点も交えながら、できるだけ分かりやすくご紹介していきます。
目次
ブランドロイヤリティとは?
さっそくですが、ブランドロイヤリティとは「あるブランドのことが大好きで、ずっと使い続けたい!」という気持ちのこと。
例えば、こんな経験ないですか?
- 「このスマホメーカーの新製品は必ずチェックする!」
- 「このコーヒーチェーン以外考えられない!」
- 「この化粧品ブランドなら間違いない!」
- 「このスニーカーブランドの新作は絶対に欲しい!」
- 「このアパレルブランドの世界観が大好き!」
そう、これらすべてがブランドロイヤリティの表れなんです!特に最近は、商品やサービスを「持っている」「使っている」だけでなく、そのブランドの世界観やストーリーまで含めて愛着を持つ人が増えているのです。
単なる「いつも買う」とは違うの?
実は、ブランドロイヤリティには2つのタイプがあると考えています。
行動的ロイヤリティ
まず、行動的ロイヤリティについて見ていきましょう。これは、文字通り行動の習慣から生まれるロイヤリティです。例えば、「近所にあるから、いつもあのスーパーで買い物をする」というような、単純な習慣による継続的な利用がこれにあたります。このタイプのロイヤリティは、特に強い愛着や好意があるわけではなく、「特に不満がないから続けている」程度の関係性です。便利だから、習慣だからという理由で選び続けているだけなので、もし近所により良いお店ができたり、より魅力的な商品が見つかったりすれば、すぐに乗り換えてしまう可能性が高いのが特徴です。
Check Point
- ただの習慣で買っている
- 「近くにあるから」「いつも使ってるから」という理由
- 「特に不満はないから続けている」程度の関係
- 他のブランドの方が良さそうなら簡単に乗り換えちゃう
こんな行動です!
- 「会社の近くにあるから、いつもあのコンビニでお昼を買う」
- 「ポイントが貯まっているから、いつものドラッグストアで買い物する」
- 「面倒だから、ずっと使っている携帯キャリアを変えない」
- 「両親が契約しているから、なんとなく同じ生命保険会社を選んだ」
- 「特売で安いときに買うから、結果的にいつもこのスーパーの食材を使っている」
- 「職場の自動販売機だから、毎日同じメーカーのコーヒーを飲んでいる」
- 「引っ越し前から使っていたから、そのままその銀行口座を使い続けている」
- 「定期券が使えるから、いつもこのガソリンスタンドで給油する」
感情的ロイヤリティ
感情的ロイヤリティは、より深い絆で結ばれた関係です。このタイプのロイヤリティを持つお客様は、そのブランドのことを心から好きで、単なる商品やサービス以上の価値を見出しています。
例えば、「このブランドの環境への取り組みに共感して、少し高くても選んでいる」というように、ブランドの価値観や理念に共感し、それを支持する気持ちが強くあります。
新商品が発売されるたびにワクワクし、たとえ価格が少し高くても、そのブランドを選び続けるでしょう。このような感情的なつながりは、一朝一夕には築けませんが、一度築かれると非常に強固なものとなります。
Check Point
- そのブランドが本当に好き!
- 「このブランドの価値観に共感する」
- 「ちょっと高くても、このブランドがいい!」
こんな行動です!
- 「このジムは一人ひとりの目標に合わせてプログラムを組んでくれて、トレーナーさんが本気で向き合ってくれる。高額だけど、続けたいと思える」
- 「このシャンプーブランドは自然由来の原料にこだわっていて、その姿勢に共感できる。値段は高めだけど、これじゃないと落ち着かない」
- 「新機能の使い方を教えてくれるコミュニティがあって、同じ製品を使う人との交流が楽しい」
- 「リフォームを依頼した工務店で、職人さんの仕事への誇りに感動。その後の小さな修繕も、必ずここに頼んでいる」
- 「オーナーシェフの食材への想いに感動して、季節のコース料理を楽しみに通っている」
- 「この焙煎所は生産者の方との関係を大切にしていて、毎月の新豆の説明を聞くのが楽しみ」
- 「このメーカーは修理対応が丁寧で、10年前の製品でも真摯に向き合ってくれる。この信頼感が次の買い替えでも決め手になる」
企業が目指すべきなのは行動的ロイヤリティ?感情的ロイヤリティ?
企業が目指すべきは、感情的ロイヤリティの構築です。なぜなら、感情的ロイヤリティは、価格や利便性だけでは揺るがない、真の意味での「ファン」を作り出すからです。
感情的ロイヤリティを持つお客様は、そのブランドの良さを周りの人に自然と伝えたくなり、結果として強力な口コミの発信源となってくれるのです。
ブランドロイヤリティって、なぜ大切なの?
「ブランドロイヤリティを高めることが大切」とよく言われますが、具体的にどんな意味があるのでしょうか?今日は企業にとってのメリットについて、分かりやすく解説していきます。
企業にとってのメリット
お客様との関係が長く続く!
まず最も大きなメリットは、お客様との関係が長く続くということです。実はビジネスの世界では、新しいお客様を見つけるよりも、既存のお客様との関係を大切にする方がずっとコストがかかりません。具体的には、新規のお客様を獲得するコストは、既存のお客様を維持するコストの5倍以上もかかると言われています。つまり、ブランドロイヤリティの高いお客様が増えれば増えるほど、企業は安定した収入を見込むことができ、長期的な経営の安定につながるんです。
価格競争に巻き込まれにくくなる!
あと価格競争からも抜け出せるようになります。ブランドロイヤリティが高まれば、お客様は「安いから買う」という理由だけでなく、「このブランドだから買う」という理由で商品を選んでくれるようになります。
例えば、サステナブルアウトドアブランドの「Snow Peak」を見てみましょう。キャンプ用品は決して安価ではありませんが、多くのファンが「Snow Peakのギアじゃないと落ち着かない」と言って選び続けています。
ファンが自然と増えていく!
最後はファンが自然と増えていくということ。ブランドロイヤリティの高いお客様は、自然とそのブランドの良さを周りの人に伝えたくなります。「このブランド素敵だよ!」「私もこれ愛用してるの!」という会話が生まれ、新たなファンを呼び込んでくれるんです。この口コミの力は、どんな広告よりも強力で、結果としてブランドの価値がどんどん高まっていきます。
どうやってブランドロイヤリティを作る?=感情的なつながりこそ大事!
徹底的な個別対応 商品・サービスの背景にあるストーリーの共有 コミュニティ形成による価値の創造 スタッフの情熱や誠実さが伝わる接点 長期的な関係性を大切にする姿勢
ブランドロイヤリティの強さとは、お客様との「心のつながり」にあります。
では、具体的にどのようにしてその絆を築いていけばいいのでしょうか?
絶対に必要なのはストーリー
現代はユーザーはみんな目がこえているので、単に「良い商品です」「便利なサービスです」と言うだけでは、お客様の心には響きません。
なぜこの商品やサービスを作ることになったのか、どんな想いを込めているのか、そういったストーリーこそが、お客様の心を動かすのです。
例えば、パタゴニアが掲げる環境保護。製品の修理サービスを積極的に推進し、むしろ「必要のない物は買わないで」と呼びかけることさえある、その姿勢は逆説的に強い信頼を生んでいます。使い込むほどに愛着が増す製品と、その背景にある環境への真摯な思いが、深い共感を呼び、コミュニティ活動への自発的な参加を促すこともあります。
Check Point!
- なぜこの商品・サービスを作ったのか?
- どんな想いを込めているのか?
- お客様の価値観と共感できるポイントは
素敵な体験を提供する
お客様がブランドと出会ってから、実際に商品やサービスを使うまで、そしてその後も含めて、すべての接点で一貫した良い体験を提供することが大切です。
有名な例で言えば、アップルストア。
僕はアップル信者なので何度となくアップルストアに足を運んでいますが、商品を手に取る瞬間から、スタッフの対応は感動レベル。あと購入後の商品の開封体験も素敵で、すべてが特別な思い出として記憶に残るように設計されています。
Check Point!
- お客様との全ての接点で、一貫した良い体験を
- 「わぁ!すごい!」と思わず声が出る感動的な瞬間を
チームを作り上げていく
忘れてはいけないのが仲間意識の醸成。同じブランドのファン同士が出会い、つながることができる場所を作ることで、ブランドを通じたコミュニティが形成されていきます。
例えば、住宅メーカーや工務店で時々開催されている施主座談会。実際に家を建てた先輩施主さんと、これから家を建てようと考えている方が話し合うきっかけをつくってあげる。そうすることでカタログやモデルハウスだけでは分からない「リアルな暮らし」が共有されていきます。「キッチンのここが使いやすくて助かっています」「子どもが小さい時は収納をこう使っていました」といった生の声は、これから家づくりを始める方にとって何よりも価値のある情報ですよね。
Check Point!
- この仲間に入りたい!と思わせる
- ブランドを通じて、お客様同士がつながれる場所を作る
- 同じ価値観を持つ仲間との出会いの場にすること
双方向コミュニケーション
かつての一方的な情報発信の時代とは異なり、今では様々な形でお客様との対話が可能になっています。SNSの登場により、お客様側からも積極的に関わることができる時代になりました。
例えば、カメラメーカーが運営するSNSコミュニティでは、ユーザー同士が撮影テクニックを共有したり、お気に入りの撮影スポットを紹介し合ったりしています。ブランド側も単なる商品情報の発信だけでなく、ユーザーの投稿へのきめ細かな返信や、印象的な写真のシェアを行うことで、コミュニティの活性化を図っています。
一方、リアルな場での交流も重要性を増しています。写真教室や料理教室、アウトドア体験会といったイベントは、単なる商品説明の場を超えて、共通の興味や価値観を持つ人々が出会う場となっています。
こんな例で感情ロイヤリティを高めてみては?
パーソナルジムでの体験
あるパーソナルジムでは、入会時に2時間かけてカウンセリングを行います。「なぜ運動を始めようと思ったのか」「どんな生活を送りたいのか」といった深い対話を通じて、その人らしい目標設定をしていきます。
トレーナーは単に運動メニューを提供するだけでなく、生活習慣の改善から食事の相談まで、総合的なサポートを提供。特に印象的なのは、LINEでの日々のやりとり。「今日は疲れているようですが、どんな一日でしたか?」という何気ない声かけから、その日の体調に合わせたメニュー調整まで、きめ細かなケアを行っています。
月額料金は一般的なジムの3倍以上しますが、「自分の健康に投資している」という実感があり、継続を迷うことはないそうです。
オーガニックコスメブランドの取り組み
某オーガニックシャンプーブランドは、商品パッケージに二次元コードを付けています。これを読み取ると、使用されている原材料の調達過程や生産者の想いを動画で見ることができます。
例えば、主原料のラベンダーは、契約農家で無農薬栽培されています。収穫時期や天候による品質の違いまで細かく説明され、毎月のニュースレターでは、畑の様子が定期的に共有されます。
さらに特徴的なのは、全成分の選定理由を詳しく公開していること。「なぜこの成分を選んだのか」「他の選択肢は検討したのか」といった開発過程の試行錯誤まで、包み隠さず発信しています。
「値段は高いけど、これだけ丁寧に作られているなら納得」「安心して使える理由が分かるから、他のブランドに浮気する気にもなれない」という声が多く聞かれます。
離乳食ブランドの信頼構築
ある離乳食ブランドでは、製造工場をバーチャルツアーで公開しています。原材料の入荷から製造、出荷までの全工程を、360度カメラで見学できる仕組みです。
特に印象的なのは、品質管理の徹底ぶり。例えば野菜は、契約農家との直接取引だけでなく、残留農薬検査を独自基準で実施。その結果データもウェブサイトで公開しています。
また、管理栄養士による無料相談窓口を設置し、離乳食の進め方や食物アレルギーの相談にも対応。「不安なときにすぐ相談できる」という安心感が、強い信頼につながっています。
インスタグラムでは、実際に使用しているママたちの声や離乳食レシピを紹介。同じ悩みを持つ親同士のコミュニティが自然と形成され、商品を超えた価値が生まれています。
老舗コーヒー焙煎所の取り組み
創業40年の焙煎所では、毎月第一土曜日に「生産者とつながるコーヒーの会」を開催。その月の新豆について、生産地の様子や農家の方々の取り組みを、写真や動画を交えて紹介。時には現地とオンラインでつないで、生産者の方から直接話を聞くことも。
参加者からは「コーヒーを飲むたびに、生産者の方の顔が思い浮かぶようになった」「豆の個性を理解することで、より深く味わえるようになった」という声が。単なる商品販売を超えた、コーヒーを通じた文化交流の場となっています。
工務店の「100年お付き合い」
ある工務店では、リフォーム完了後も定期的に「お住まい見守り訪問」を実施しています。些細な不具合や相談にも丁寧に対応し、必要に応じて職人さんが駆けつけます。
印象的なのは、職人さんの仕事への姿勢。「この家で家族の思い出が作られていくと思うと、手を抜くことなんてできません」という言葉に、多くの施主さんが感動したと言います。完了時の引き渡し写真には、関わった職人全員のサインと、家族への温かいメッセージが添えられています。
オーナーシェフの想いが伝わるレストラン
予約の取れない人気店として知られる、あるイタリアンレストラン。シェフは毎朝、契約農家を直接訪問して食材を選びます。その日のメニューは、生産者との会話や食材の状態を見て決めるそう。
月に一度開催される「生産者を囲む会」では、シェフと生産者が食材への想いを語り、参加者と一緒に新メニューを考案することも。「食材の物語を知ることで、料理がより一層美味しく感じられる」と、常連客は語ります。
効果はちゃんと確認しよう!
ブランドロイヤリティの構築に向けて様々な取り組みを行った後は、その効果をしっかりと確認することが大切です。でも、「お客様の心のつながり」という目に見えにくいものを、どうやって測ればいいのでしょうか?
数字で見ること
実は、ブランドロイヤリティの効果は「数字」と「気持ち」の両面から見ることができます。まず数字の面では、お客様が生涯を通じて使ってくださる総額(ライフタイムバリュー)を見ることができます。例えば、毎月定期的に商品を購入してくださるお客様は、そのブランドに強い信頼を寄せているといえるでしょう。また、リピート率、つまり一度購入したお客様が再び商品を買ってくださる割合も、重要な指標となります。さらに、「友達に勧めたい!」という推奨意向(NPS:Net Promoter Score)も、ブランドへの信頼度を表す大切な数値です。
気持ちで見ること
一方で、数字だけでは見えてこない「気持ち」の部分も重要です。例えば、施主座談会でのお客様の笑顔や、SNSでの自発的な投稿、イベントへの積極的な参加など、ブランドへの好感度は様々な形で表れます。また、カスタマーサポートへの問い合わせ内容や、アンケートでの自由回答からも、お客様の満足度を読み取ることができます。さらに、ブランドコミュニティでの発言頻度や内容からは、お客様がどれだけブランドに深く関わってくださっているかが分かります。
これらの指標は、単独で見るのではなく、総合的に判断することが大切です。例えば、数字としてのリピート率は高くても、SNSでの言及が少ないケースもあれば、その逆もあります。両面から見ることで、より正確にブランドロイヤリティの状況を把握し、改善のヒントを見つけることができるのです。
さいごに
ブランドロイヤリティは、一朝一夕には作れません。でも、一歩一歩、お客様との信頼関係を築いていけば、必ず実を結ぶはずです。
大切なのは、「なぜこれをやるのか?」というWHYをしっかり考え、そこから「何をするか」「どうやるか」を組み立てていくこと。
お客様の立場に立って考え、データと感性のバランスを取りながら、継続的に改善していく。その積み重ねが、強いブランドロイヤリティを作っていくんです!
みなさんも、ぜひチャレンジしてみてくださいね!