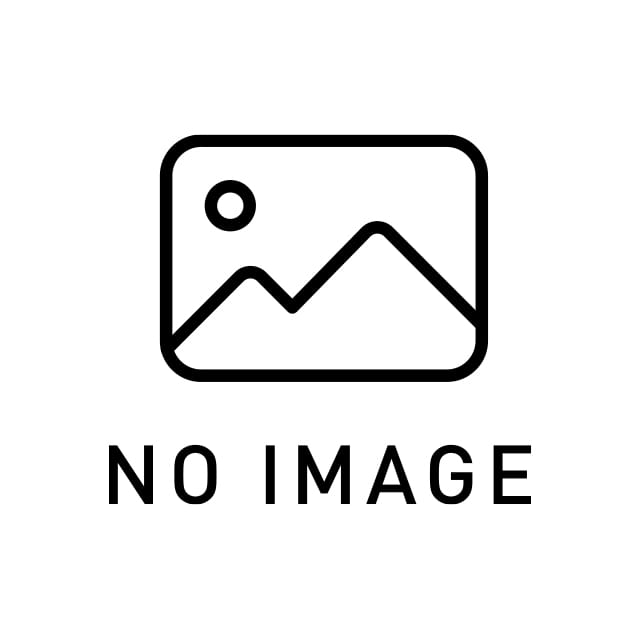ブランドセイリエンスってどんな意味?【←めちゃ丁寧に解説します】

デザインメンターのたかりょーです。
ブランド戦略を立てる上で重要な概念「ブランドセイリエンス」。
経営者やクリエイターなら、ブランディングとの関連性の中で「ブランドセイリエンス」がどういう状況で使用されるのか、どんな意味は持つかは知っておいた方がいいです。
目次
「ブランドセイリエンス」とは?
「ブランドセイリエンス」とは、消費者が購買という意思決定を行う際に、心の中でブランドがどう想起されるかを示す傾向のこと。
もっと分かりやすくいうなら、「ブランドの思い出しやすさ」や「心の中の想起傾向」といえばいいでしょうか。
ブランドセイリエンスは、消費者が製品やサービスを選ぶ際に、特定のブランドを自動的に思い出し、そのブランドに対して有する感情や印象に基づいて選択するため、ブランドセイリエンスを高い状態にキープすることって、商品を選んでもらうときには、すごく優位な立場を築けるわけなんです。
ここでいう感情というのは、“好感”というポジティブな感情です。
だから単純に「ブランドセイリエンスが高い」とは「消費者がブランドに対して好印象を持っていて、思い出されやすい状態である」と同義であって、消費者はそのブランドを高い信頼性を持っているからこそ、そのブランドの製品・サービスを選ぶ可能性が高い状態であるということにもつながります。
そもそもセイリエンスという言葉の意味、知っている?
サイリエンス(salience)とは、私たちの心の中である物事が「パッと目立つ」「すぐに思い浮かぶ」という特徴のことです。
例えば、「新しい靴が欲しいな」と思った時、すぐに頭に浮かんでくるブランドってありますよね。ナイキやアディダスなど、普段から目にする機会が多いブランドが、自然と思い浮かんでくる。これがまさにサイリエンスの働きなんです。
面白いのは、サイリエンスは単に「そのブランドを知っている」というだけの話ではないということ。毎日意識して考えているわけじゃなくても、必要な時にスッと頭に浮かんでくる。
例えば、コーヒーが飲みたくなった時に「スターバックス」を思い浮かべたり、スマートフォンを買い替えようと思った時に「iPhone」が頭に浮かんだり。こういった自然な想起が、私たちの選択や行動に大きな影響を与えているんです。
つまりサイリエンスとは、ブランドが私たちの日常生活の中に自然と溶け込み、単にブランドを「知っている」という状態から一歩進んで、日常のふとした瞬間に自然と意識に浮かびあがってくる存在なんです。
ブランドセイリエンスは「記憶構造」と深い結びつきがあります
ブランドセイリエンスは『ブランドが人々の心のなかにどのように占めているか』を示します。だからブランドと記憶との間に構築されるネットワークの質と量に影響されます。
つまり、「記憶構造」と非常に密接な関係にあります。
人間の脳って、情報を処理する際に膨大な量のデータを取り入れて、それを一定のパターンやルールに従い結びつけて、記憶を形成しています。
このパターンやルールのことを「認知スキーマ」と呼びます。
ブランドセイリエンスは、実は消費者があるブランドに対して持つ「認知スキーマ」の一部なのです。ブランドセイリエンスは、消費者があるブランドを認識する際の“結びつき・傾向”なので、実際はそのブランドに関する情報をどのようなルールやパターンで処理するか?ということなんです。
例えば、消費者がナイキのロゴを見たとき、好印象なのか?何も感じないのか?というのは、その消費者が持つブランドセイリエンスによって決まります。もし消費者がナイキに対して「なんかいいなあ」というイメージを持っているなら、そのロゴを見た際には、「なんかいいなあ」というなんとなく良い感じを持つ傾向が強くなるです。
このようにブランドセイリエンスは、消費者があるブランドに対して持つ認知スキーマの一部であること、そしてそのブランドに対する反応や評価、ひいてはその先にある信頼感や忠誠心に影響を与えているんです。したがって、ブランドセイリエンスを高めることは、ブランドが消費者に認知されたり、思い出されたり、親しまれたりするのに、とても大切な要素なのです。
ブランドセイリエンスが高い状態ってどういうこと?
「ブランドセイリエンスが高い状態って具体的にどういうこと?」「どんなメリットがあるの?」という人向けに。
ブランドセイリエンスがもたらす効果をご紹介しますね。
選ばれる確率が高まる
僕はこれが一番のメリットだと思っています。
つまりブランドセイリエンスが高いと「他社ブランドよりも先に思い出してもらえるようになる」ので、製品・商品の選ばれる確率が高まるということです。
消費者はなにか商品やサービスを検討・購入しようとするとき、購入候補として複数のブランドを比較検討しています。
もしその際、真っ先に思い出してもらえるブランドになればどうでしょうか?当然ながらその後の選択プロセスにおいて有利になりますよね。
例えば、ある消費者がスマートフォンを買おうかな?と思った時。さまざまなメーカーの中でAppleとサムソンの2つのブランドを検討しているとします。
この場合、両社のスマートフォンがほとんど似たような機能があって、価格もほぼ同じであったとします。その際、消費者はどちらを選ぶか悩むことになりますよね。
ここでブランドセイリエンスの登場です。もし消費者が広告なり、知人からの話なりで、Appleの良い印象を持っているとしたら、その人はAppleのスマートフォンを選ぶ確率が高まりますよね。
これが人だけでなく、その他多数の人まで含めて「Appleのブランドセイリエンスが高い」ならば、彼らの脳裏には強く印象づけられていることになり、選択の決め手になる可能性が高いからです。
ロイヤリティが高まる
これはどちらかというと、体験後の話ですね。
ブランドセイリエンスが高ければ、消費者のロイヤリティが高まります。なぜなら消費者はブランドをより早く思い出し、信頼しているからです。そして継続的に購入する可能性も高まっていきます。
ロイヤリティの高い消費者を増やすことは、事業にとって大きなメリットがあります。例えば、消費者はブランドの新商品やキャンペーンに興味を持ってくれるかもしれません。また友人に口頭で「このブランドって〇〇が良いんだよ」と広めてくれるかもしれない。リアルじゃなくてもSNSとかでシェアしてくれるかもしれません。
このように、ブランドセイリエンスが高いと、消費者のロイヤリティが高まります。そのため、ブランドコンサルタントとしては、ブランドセイリエンスを高めるための施策を積極的に行うことが必要です。
POINT!
ロイヤティはブランドセイリエンスに支えられています。一般的にロイヤリティは消費者の好き嫌いかと思う人もいるかもしれません。でもブランドロイヤリティを育たせるためには、ブランドが消費者が認識できるように目立たせる必要があります。
価格コントロールができる
ブランドセイリエンスが高ければ、ブランド力が強化されていることと同義です。もしブランド力が強化されているなら、消費者は「高い価格でも購入したい」という気持ちが湧いてきます。
つまり、ブランドセイリエンスが高いブランドは、価格コントロールもしやすくなるのです。
ただし注意が必要なのは、もし「安さ」や「お手軽さ」という部分で、ブランドセイリエンスが高い場合。これはそもそもが価格の部分で惹かれている消費者が多いので、プレミアム価格の商品を出しても、惹かれないかもです。
ブランド拡張がしやすい=消費者が受け入れやすくなる!
ブランドイメージを維持しながら、新しい市場への進出などにも有利に働くでしょう。
例えば、あるブランドが高いブランドセイリエンスを持っている状態で、そのブランドが新たに別の業界に進出し、新商品・サービスを提供したとしましょう。消費者はそのブランドに対して持っている信頼性に基づいて評価するので、それらに高い期待感を持つようになりますよね。
当然ながら全面的に認めることはしないとは思いますが、ブランドセイリエンスが低い企業と相対的に比較したときには、必ず”高い期待値”があると思います。
反対に新しい商品・サービスを提供することが、安定や話題性という部分でも、既存のブランドイメージ維持にもつながります。
ブランドセイリエンスを高める方法は?
ブランドアイデンティティを明確にする
まず最初にするべきはブランデンティティを明確にすることです。
ブランドアイデンティティが明確になれば、消費者にブランドの価値観や特徴的な要素、ミッション伝えられます。それは消費者に対して「ブランドのイメージ=らしさ」を記憶を新たに構築させることができます。それを定着させれれば、ブランド想起の傾向を高められます
ここでいうブランドアイデンティティとは、ブランドが本来持っている特徴や価値観、スタイルなどの要素を、言語化や視覚化を通じて表現・明確にしたものです。これを明確にすることで、消費者がブランドを認知しやすくなり、ブランドが想起される傾向が高まります。
例えばブランドストーリーを作り上げるのもその一つ。ブランドストーリーは、ブランドの歴史や背景、製品開発の過程などをストーリーテリングの力からを借りて、感情的・論理的どちらの要素からもブランドの魅力やストーリーを伝えることができます。
それを継続的に発信しよう
ブランドアイデンティティの継続的な発信は、ブランドイメージを消費者に定着させる上で非常に重要です。長期間にわたって安定的にブランドから情報やメッセージを受け取れば、消費者の記憶の枠組みの中に組み込まれます。
そうなればあらゆるシーンで「想起の傾向」を作ってあげられます。
消費者は多様な情報や刺激に晒されています。日常生活に忙殺されれば、ブランドの存在なんて簡単に忘れられてしまいます。そのため継続的に発信することで、消費者がブランド想起の確率を高め、ブランドイメージを強化させるのです。
例えば広告なんかはまさにそうで、独創的なメッセージを継続的に発信してあげることで、彼らの記憶構造を刷新してあげているんです。それがブランドセイリエンスを維持/構築につながるんです。
一貫性を保つようにしよう
継続的に発信するだけでなく、そこに一貫性が必要。
ロゴやタグライン、広告やマーケティングコミュニケーション等々。全てのコンタクトポイントにおいて、一貫性を持ったブランドメッセージを伝えるべきです。
それは商品やサービスの品質や使いやすさの向上はもちろん、店舗の雰囲気やディスプレイ、接客態度、オンラインストアのユーザビリティに至るまで、消費者がブランドを“体験””接する”ポイントです。
全てのコンタクトポイントに一貫性がないと、消費者は混乱したブランドのイメージを持つようになり、逆に、ブランドに対する信頼の低下につながる可能性があるからです。
例えば、Aブランドがある商品を高級感のあるデザインで販売していたとします。しかし、その後同じブランドから同じ商品が、安っぽいデザインで販売されるようになったとします。このように一貫性がないと、消費者はブランドの信頼性に疑問を抱き、商品購入に踏み切れなくなる可能性があります。
>商品体験とは?
ブランドセイリエンスの測定方法は?
「具体的にどうやってブランドサイリエンスってはかるの?」
このように疑問に思われる方もいると思います。
ブランドセイリエンスを測定する方法は大きく分けて2つあります。
それは下記のとおりです。
- 定量調査
- 定性調査
それぞれ具体的にみていきましょう。
定量調査
定量的な測定方法は消費者がブランドに対してどのようなイメージを持っているか、またそのブランドをどの程度知っているかを数値化することで、ブランドセイリエンスを客観的に測定します。
代表的な例としてインタビュー調査やアンケート調査ですね。
アンケート調査による測定
特定のテーマについて多数の回答を集め、統計的に分析する方法です。質問の設計がなによりも重要で、適切な質問によって必要な情報を効果的に引き出すことができます。
例えば
- 「このブランドに対して高級感を感じますか?」
- 「このブランドの商品を購入したいと思いますか?」 などの質問を通じて、ブランドイメージを数値化することができます。
行動データの分析
行動データの分析では、消費者がブランドに対してどのような行動をとっているかを分析することで、ブランドセイリエンスを測定します。
例えば
- ウェブサイトへのアクセス数
- 購買履歴データ
- 顧客属性分析 など
定性調査=3つのアプローと方法
結局のところ、ブランドを選ぶのは僕たち消費者なんです。だからこそ、実際の消費者の声を直接聞くことって、すごく大切なんですよね。
定性的な測定方法では自由な意見交換の場を設けて、リアルなやりとり・ディスカッションを通じて、ブランドの印象を把握します。
具体例としては、フォーカスグループ、フリーリスト法、グループディスカッションですね。
フォーカスグループインタビュー
フォーカスグループインタビューは数名の消費者が集まって、ブランドについて自由に意見を交わす場です。例えば、新しい化粧品ブランドについて「この香りの印象は?」「パッケージを見てどう感じる?」といった話題で対話を深めていきます。
フリーリスト法
フリーリストは消費者にブランドから連想される言葉やイメージを自由に書き出してもらいます。例えば「このブランドを思い浮かべた時に、どんな言葉が思い浮かびますか?」という質問から始め、出てきた言葉を分析することで、そのブランドが持つ認知的な特徴や印象を理解することができます。
グループディスカッション
グループディスカッションは少人数のグループで、より深い対話を重ねていく手法です。参加者同士の会話の中から、新しい気づきが生まれることも。「なぜそう感じるのか」「どんな時にそのブランドを選びたくなるのか」といった掘り下げた質問を通じて、本音の部分に迫ることができます。