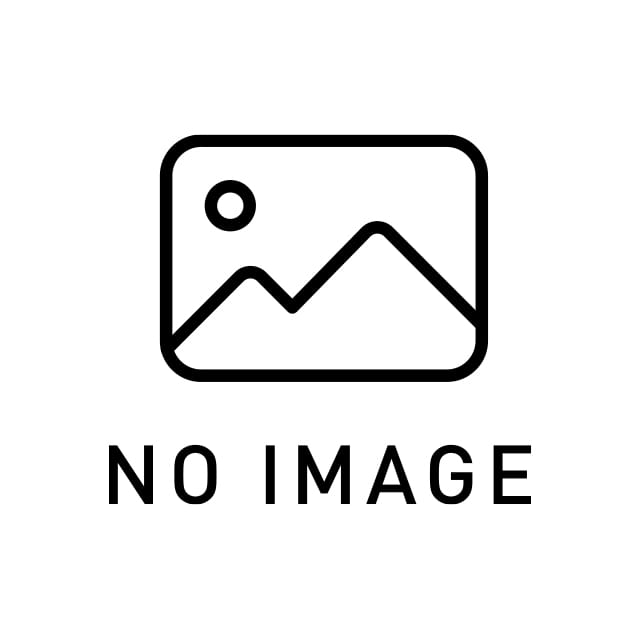新人デザイナーを教育するコツ【タイプ毎の教育/実体験】

経験を積むにつれて、デザイナーは後輩や新入社員の教育・指導を求められることが増えます。しかし、長年プレイヤーとしてデザインの最前線で活躍してきた方々の中には、「自分のような経験を、どうやって教えられるんだろう」「私のやり方は私にしかできないのでは」と、教育に対して不安を感じる方も多いのではないでしょうか。
僕はWebディレクターとして、10人以上のデザイナーと関わりながらフィードバックや指導を行っています。今回は、そんな新人デザイナーの教育方法について、私の経験から得た知見を伝えていこうと思います。
目次
そもそも新人デザイナーって、どんなことに迷っている?

たまたま新人デザイナーと話している時に、相談に関する興味深い話を聞く機会がありました。新人デザイナーは、先輩に相談する際にさまざまなためらいや戸惑いを感じているようなんです。
彼らが抱える主な悩みは以下のようなものが多いです。
- 質問をためらう→自分の質問や悩みが「つまらない」や「初歩的すぎる」と思い、相談をためらうことがあります。
- 先輩への不要な配慮→先輩の貴重な時間を奪ってしまうのではないかと心配し、相談を躊躇する傾向があります。
- 評価されることへの不安→自分の能力や作品が低く評価されるのではないかという恐れが、相談を難しくします。
- タイミングの迷い→いつ、どのように相談を持ちかけるべきか、迷ってしまうことがあります。
- 言語化の難しさ→自分の悩みや疑問を明確に言語化できず、何を聞くべきか整理できないこともあります。
僕たちはこうした彼らの悩みを理解して、新人デザイナーが安心して相談できる環境を整えていかないと、成長をうまくサポートすることができません。
新人デザイナーへ教育するコツ【実践ノウハウ】

心理的安全性=相談しやすい環境づくり
僕の経験上、多くの新人デザイナーは、「こんな質門していいのかな?」「先輩は忙しそうだから、時間を奪うのは避けたほうがいいかも…」と感じ、相談をためらうことがあります。
でもそもそも、相談しにくい雰囲気をつくっているのは「あなた自身」かもしれません。
そこで重要となるのが「心理的安全性」という概念。これは相談しやすい環境を整えるための基本です。
心理的安全性とは、質問することへの抵抗感を減らし、自分の意見や質問を自由に表現できる雰囲気をつくってあげること。
心理的安全性を確保するために、例えば僕が意識していることとしては、下記があります。
- 「いつでも質問してください」と明確に伝える。
- 質問のための「質問タイム」を1日の中に設ける。
- 「質問することは学ぶ姿勢の表れであり、どんな質問も成長につながる」といった価値観を共有する。
質問すること自体が悪いものではないと伝えて、質問することへの抵抗感を軽減し、自分の意見や疑問を自由に表現できる時間を確保することで、ぐっと相談しやすい環境につながっていきます。
否定的な評価を避け、建設的なフィードバックを心がける
先輩デザイナーは経験がたくさんあるがゆえに、つい細かな点に目が行きがち。「これではダメ」「全然理解していないね」と心のない否定的なフィードバックは、新人デザイナーを萎縮させてしまいます。
僕がフィードバックを行う際に意識しているのは、まず良い点をちゃんと認めて褒め、その後に改善点を指摘すること。いわゆるポジティブフィードバックというやつです。
褒めるのはちょっとしたことでもいいです。「配色のバランスがとても良いですね」とか、「この装飾は素晴らしいです」といった感じ。
そして改善点を指摘する際は、単に「これが悪い」と言うのではなく、どうすればより良くなるかを具体的に示すことが重要。
例えば、「このボタンの配置を画面右下に移動させると、ユーザーの操作性が向上するよ」「お客さんが求めているのはもう少し柔らかい雰囲気じゃないかな?」というふうになぜこの改善がいいのか?と根拠を示すようにしてあげます。
というのもデザインの本質は「なぜそうしたのか」という表現の意図を理解するあるからです。形やレイアウトの理由、色の選び方、余白の取り方…。こうした判断の背景にある考え方を丁寧に伝えることで、デザイナーは意図を理解しながら自分なりの表現ができるようになっていくのです。
このように良い点を認めつつ改善点も提示することで、バランスの取れたフィードバック、つまり建設的なフィードバックを行うことができます。
この実践を繰り返し、好サイクルを繰り返すことで、着実にスキルアップが図れます。
全部教えない〜自主性の尊重〜
ついつい先輩心で「手取り足取り全部教えてしまう人」がいると思いますが、教育という観点からは全部教えないほうがいいです。
その理由は、「自分で考えるクセ」が見につけられないからです。
ひとは誰しも楽な方向に流れやすい性質をもっています。特にデザインは正解がないからこそ、すぐに答えを求めたくなる気持ちはとても自然なことです。
しかし常に答えを与えられると、自分で考えなくなって、常に指示を待つ姿勢が身についてしまいます。実際、このようなデザイナーは割りかし多くて、自分で答えを求めるべきなのに、それを探す能力や癖が身についておらず、完全な他力本願になってしまっています。(最悪なのは本人がそのことに気づいていないこと・・・)
でも考えてみてください。そもそもデザインはクリエイティブな分野です。自ら考え、試行錯誤する中で独自の発想がうまれてきます。
例えば、配色で悩んだとき、「先輩、これでいいですか?」と聞く前に、まず「なぜこの色を選んだのか」を自分に問いかけてみる。レイアウトを決めるとき、「これで大丈夫ですか?」と確認する前に、「この構成で本当に伝えたいことが伝わるだろうか」と自問自答してみる。
だからこそ、教える側としては、全てを教え込むのではなく、コメントでヒントを示してあげたり、対話をしたり、改善の方向性を示唆してあげたりすることが重要です。新人デザイナー自ら考える余地を残し、答えにたどり着くよう導いてあげることのほうが大切です。
デザイン課題を定期的に行い、みんなでフィードバックを行う
もしあなたの会社に複数のデザイナーがいて、チームとして動いているなら、定期的にデザインチャレジや共有会を開催することもおすすめ。
デザイン課題とは、定期的に小規模なデザインのテーマを設定し、チーム全体で取り組む活動のこと。各自の結果を共有し、互いにフィードバックを行うことで、質問や相談が自然に生まれる環境を作ることができます。
例えば、月1回のデザインチャレンジではこんな取り組みができます。
- 「同じ商品の広告バナーを、ターゲット層を変えて制作」
- 「既存のランディングページを、異なる目的で再デザイン」
- 「架空のブランドのロゴデザインを、与えられたキーワードをもとに作成」
そして作品を共有する際は、単に「できました!」で終わらせるのではなく、以下のような視点で対話を深めていきます。
- なぜその表現方法を選んだのか
- 試行錯誤したポイントは何か
- 他のアプローチも検討したか
- どんな気づきがあったか
このようにチームメンバーが自身の失敗経験と取り組みのなかで学んだことを共有する機会を設けると有効といえるでしょう。
チームでこの活動を続けることで、デザインチーム全体の成長にもつながって、より良いデザインを生み出す土壌を築くことができます。
個人のメンタルフォローも
新人デザイナーの指導では、技術面だけでなく、精神的なサポートも大切です。デザイナーは自分の作品に対してプライドを持っているため、心配性な一面があります。彼らの「自信」を高めることは、自己効力感を育む上でも非常に重要です。
おすすめなのは、小さな成功や進歩を積極的に認めて褒めることです。例えば、1日の終わりに進捗を話し合う機会を設け、「今日はどうだった?」「何か困っていることはある?」といった質問を日常的に投げかけると良いです。
もし彼らが何かに詰まっていれば、自然と相談してくるはず。このような関係づくりが、先ほど述べた心理的安全性の確保にも繋がります。
さらに、仕事以外の場面でランチに付き合うことで、仕事という枠を超えたオープンな関係性を築けます。これにより、より信頼される存在となることができるでしょう。
【タイプ編】新人デザイナーの個人の特性に合わせて教育方法をご紹介

これまでさまざまなコツをお伝えしてきましたが、僕の経験から特に重要だと思うことをお伝えします。それは、デザイナー全員に同じ方法で指導しないことです。デザイナーは同じ職業に就いていても、それぞれ異なる個性を持っています。
性格も違えば、強み、弱み、学習スタイルだって人によってことなります。だからこそ、新人デザイナーごとに指導方法をカスタマイズしたほうが良いです。
ここでは、いくつかのタイプに分けて、それぞれに適した指導方法の例を示します。
言語化が得意なデザイナー
言語化が得意なデザイナーは自分の考えやデザイン要素を言葉で表現するのが上手です。(僕の知っているデザイナーのなかでも言語化が得意なのはほんとうに稀。だからとても貴重な人材です)
ですから彼らに対しては、クライアントや社内向けのプレゼンテーションを積極的に任せ、デザイン意図を言葉で説明する機会を増やしてあげるといいです。というのも社内メンバーに対しては説明ができても、社外の人(デザインの知識がない素人)に説明するのが苦手というデザイナーも多いからです。
プレゼンテーションを通じて、自分のデザインに対して批評するスキルが身につき、表現への自信が深まります。これにより、クライアントに対して提案するときに納得感のあるデザインを作れるようになるでしょう。
さらに、言葉だけでなく、説明の際に使用するビジュアル資料を作成する練習も促すと良いです。これにより、バランスの取れたプレゼンテーションスキルを育成できます。
最終的には、後輩への指導やアートディレクションを行える人材に成長させることが期待できます。
実践型のデザイナー=いわゆる感覚派
感覚派のデザイナーは手を動かすことを好むので、実際にやってみないと理解できない・説明できない傾向があります。いわゆる感覚派のデザイナーであり、「言語化しましょう」と言ってもなかなか難しい。
とはいえ、実際に手を動かしながらアイデアを形にさせていくことが得意です。彼らの頭の中では、常にビジュアルやレイアウトが動き続けていて、その豊かな感性こそ実際の制作過程で最大限に発揮されるのです。
具体的には、適切な自由度を設定し、デザインを作成させます。ただし、完全にお任せするのではなく、配色やテイストの方向性を示しながら、手を動かしてもらいます。つまり、デザインの試行錯誤の余地を十分に確保してあげるのです。
ここで大切なのは、緩やかな方向性を示してあげること
- 目指すべきゴール
- ブランドの世界観やトーンの範囲
- 何をしてはいけないのか?
- 与えたいデザインの印象
そしてこうしたデザイナーには、言語化が苦手な点を否定せず、無理に一人で考えさせるのではなく、対話を通じて一緒に整理していきます。
「このレイアウトにした理由は?」 →「なんとなくしっくりくる感じがして…」 →「ユーザーの視線の流れを考えたのかな?」 →「あ、そうです!上から下への自然な流れを作りたくて…」
さらに、定期的な進捗確認を設け、「なぜ?」という問いかけを通じた振り返りを行います。進捗確認の際には、スケッチやラフ案を含む複数の案を見せてもらい、選択の過程について対話しながら、一緒に言語化していきます。この中で、具体的なアドバイスを通じて軌道修正も行っていきます。
自分の意見を強く主張していくるデザイナー
このタイプのデザイナーは自信を持って自分の意見を表明できますが、時には人の意見を受け入れずに、我が道を進んでいきます。
こうした自信は非常に魅力的なのですが、、、、それがほんとうにクライアントが求めていること・ニーズなのか、ユーザー目線からはどう見えるのかを、冷静に伝えることが大切です。
例えば、デザイン案を提示した際に、「このデザインはめちゃくちゃ素晴らしい!。特に〇〇の部分は個性が出ていて良いと思います。ただ、別の観点から見ると、どのような改善点が考えられる?例えば〇〇という視点はありですかね?また、このデザインに対して、ユーザーやクライアントからどんな反応が得られそう?」といった質問を投げかけると良いです。
またデザインチームに積極的に参加させ、他のメンバーと協力して一つの成果物を作り上げる経験も良いと思います。
こうした「みんなで協力する」スタイルを好まないかもしれませんが、その過程で「チームメンバーの意見をどのように取り入れたか」「フィードバックを受ける前と後で、デザインにどのような変化があったか」といった質問を通じて、協調の重要性を伝えることもできます。
なんでも鵜呑みにしてくるデザイナー
このタイプのデザイナーは、言われたことを「そうですね」「わかりました〜」とすぐに鵜呑みにしてしまう傾向があります。こうした素直さは良い態度ですが、デザイナーとしては自分の意見をしっかり持ったデザインを実践してほしいところです。
このタイプのデザイナーには、質問を促す指導が効果的です。たとえば、何か指導を行った際に「いいですね」と思ったら、すぐに「なぜそう思う?」「他にどんな方法が考えられる?」といった質問を積極的に投げかけましょう。
このようにすることで、「考える習慣」を身につけることができます。
また、デザインの各要素についても深堀りすることが重要です。なぜその選択をしたのか理由を説明できないことが多いからです。そのため、言語化の練習を繰り返すことで、自己表現力が向上し、成長につながるでしょう。
デザイナーを教育する側→あなたはデザインメンターです。

新人を教育する際、自身がメンターの役割を果たさなければならないということ。
メンターとして果たすべき役割は多岐にわたります。デザインスキルの指導(具体的なテクニックやツールの使用方法)だけではなく、クライアントへの対応方法、タイムマネジメントのコツ、ストレス管理、将来的なキャリアなどなど。
つまりデザイナーとして「デザインがうまい」だけではなだめなのです。あくまで教育する側は、各デザイナーの個性、学習スタイル、強み、弱みを深く理解し、より多くの視点から指導していく必要があるのです。そして常に学び、適応し、成長する姿勢を持ち続けることが、優れたメンターとしての基本姿勢となるでしょう。
ちなみにメンターはめちゃくちゃ難しいです。時間もかかる作業です。でも長期的に見たときに、個々のデザイナーの成長だけでなく、チーム全体の能力向上、そして組織全体のデザイン文化の発展につながっていきます。