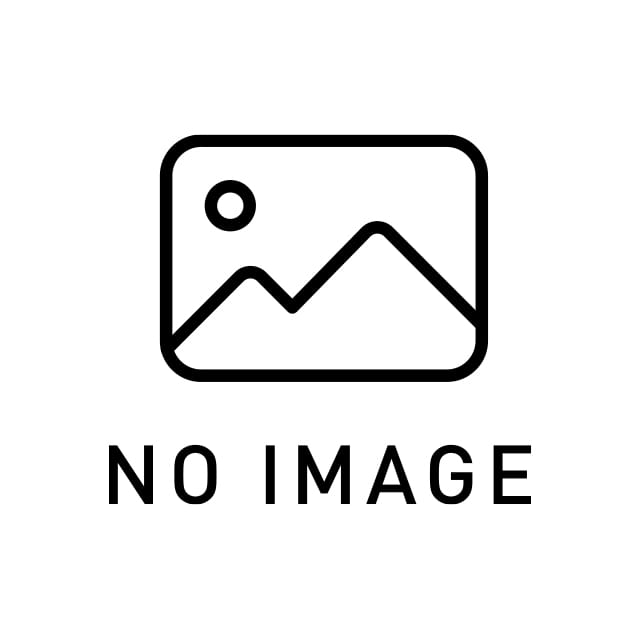「グランドマップ」とは?グランドマップでつくるブランドデザイン

中川政七商店の中川淳氏が提唱する「グランドマップ」は、経営目標を可視化するための6つの軸――環境・強み・意思・志・ポジション・ゴール――から成り立っています。
「グランドマップ=中期経営計画における定性的目標」
デザイナーがデザインするとき、あるいは企業ブランディングに携わるときには、この5要素を理解しているかどうかで、表現の“深度”がまるで変わります。
なぜこの色なのか、なぜこの言葉なのか、なぜこの空気感なのか――その根拠を経営の文脈と結びつけられる人こそが、「ブランドを形づくるデザイナー」と言えるのです。
目次
「グランドマップ」の6要素
環境|外の変化を読む力が、ブランドの起点になる
ブランドづくりの出発点は、まず「環境」を正しく読むことから始まります。
環境とは市場構造、顧客変化、業界の潮流といった外部要因の前提。いま自分たちを取り巻く市場や業界構造、顧客の行動変化、社会的な潮流をヒアリングを通じて丁寧に把握する。これが“外側の前提”です。
ここを誤ると、どんなに優れたデザイン戦略も的外れになります。
デザインは「誰に・何を・どんな時代背景で」届けるかを抜きに成立しません。市場構造を知ることは、UI設計や情報設計の起点。顧客行動の変化を読むことで、体験設計(CX)の仮説が生まれます。
強み|自社の核となる能力・資産
次に重要なのが「強み」を見極めることです。技術、人、文化、仕組み――どんな資産を持っているのかを洗い出し、それをブランドの“内側の軸”として定義します。
強みを言語化できる企業は、デザインに一貫性を持たせることができます。逆に強みが曖昧なままでは、デザインは見た目の装飾に終わってしまう。どんな貢献ができるのかを明確にし、それを視覚的に体現することが、ブランディングの基盤となります。
ちなみに中川政七商店が持つ代表的な強みのひとつが「直営力」です。自社で店舗を運営し、顧客と直接接点を持つことで、商品だけでなく体験そのものをコントロールできる。この直営の強みは、デザインにも大きく影響します。店舗の空気感、パッケージの手触り、ウェブサイトの語り口までを一貫したトーンで構築できるのは、自ら流通を握っているからこそ。つまり“売り場から理念までをデザインできる”ことが直営力の本質です。
意思|どう在りたいかを決めることで、判断基準が生まれる
この「環境」と「強み」という外と内の分析を踏まえたうえで、経営として「どう在りたいか」「どう行動するか」という意思を言語化します。
意思とは「こう在りたい」「こう行動する」という経営の決断であり、ブランディングの羅針盤となります。ここが定まると、あらゆるデザイン判断に一貫した基準が生まれます。流行を追うか、独自の価値を守るか。短期的な利益を取るか、長期的な信頼を築くか。意思の明確さは、ブランドの芯の強さを決定づける要素です。
志|社会への約束としての“未来の姿”を描く
意思を一段抽象化したものが「志」です。志とは、企業が社会に対してどんな価値を実現したいのか、どんな未来をつくりたいのかという“約束”です。環境・強み・意思の延長線上にある志は、理念の中心であり、デザインコンセプトの核になります。志を持つ企業は、プロダクトやサービスの先に“社会的な意味”を提示できる。志が明確であればあるほど、デザインは単なる装飾から、物語を語る力を持ち始めます。
ポジション|市場の中で、どこに立つかを選ぶ
最後に「ポジション」を定めます。ポジションとは、業界内でどんな役割を果たすのか、顧客にどう見られたいのかという立ち位置の宣言です。これはブランドのトーンやスタイル、デザイン表現の方向性を決める重要な要素。たとえば「工芸業界の星野リゾート」のように、比喩で語れるポジションを持つと、関わる人すべてが同じイメージを共有できます。ポジションとは、ブランドが社会に存在するための“居場所”なのです。
ゴール|理念を現実へと橋渡しする“未来の設計図”
「ゴール」は、グランドマップの最終地点であり、理念を現実に変えるための設計図です。
志やポジションで描いた理想を、どのような時間軸と成果指標で実現していくのかを定義します。ここでのゴールは、単なる数値目標ではなく、社会的・文化的成果を見据えた長期的な到達点です。
「グランドマップ」の構造的強固性
つまりグランドマップは下記のような構造になります。
- 「環境」=外の現実を見据える
- 「強み」=内の資源を見極める
- 「意思」=戦略的方向を決める
- 「志」=存在理由を定義する
- 「ポジション」=社会の中での立ち位置を宣言する
環境と強みが「現実性」を担保し、意思と志が「理念と方向性」を支え、ポジション社会的整合性を与えるようになっているわけです。
中川政七商店のグランドマップ実例
| 要素 | 内容 | 解説 (デザイン視点での意味づけ) |
|---|---|---|
| 環境 | 日本の工芸の衰退 | 「文化価値は高いのに経済的に持続しない」という社会課題。デザインは単なる造形でなく“再構築の仕組み”を考えるべき領域だと定義している。 |
| 強み | ブランドマネジメントができる/直営店という流通網 | “ブランドを構築できる力”と“顧客接点を持つ仕組み”の両輪。デザインはその一貫性を保つための仕組み設計(CI、店舗、Web、プロダクト)に貢献する。 |
| 意思 | 自社と業界を生き残らせる | 経営の焦点を「自社だけでなく、業界全体の再生」に置く。デザインも“共存・共創”を目的に使われる。 |
| 志 | 日本の工芸を元気にする! | 企業理念の中心。志を視覚・体験・言葉で表現するのがデザインの使命。商品のパッケージや店舗空間にまで“工芸の誇り”を宿す。 |
| ポジション | 工芸業界の星野リゾート | 比喩で示された「体験設計企業」としての立ち位置。職人・顧客・地域をつなぐ“場のデザイン”を担う。 |
| ゴール | 各地に“産地の一番星”を生み、100年後に『工芸大国・日本』と言われる | 短期の売上でなく、長期の文化的成果を目指す。デザインは“未来の評価軸”を見据え、普遍性と独自性の両立を目指す。 |
グランドマップがなぜデザインにおいて大切なのか?
大前提として、僕はデザインを「視覚的な表現をつくる仕事」だとは思っていません。
デザインとは、経営に役立つための思考と構造のツールです。経営が抱える課題や目的を整理し、それを「誰に」「どんな価値として」「どう届けるか」を構造化していく——このプロセスこそが“デザイン”の本質だと考えています。
その立場から見たとき、経営の意思を可視化するフレームである中川政七商店・中川淳氏の「グランドマップ」は、デザイナーにとって欠かせないツールになってきます。
1. デザインは“経営の言葉を社会の言葉に変える”仕事だから
グランドマップは経営が描く「目標設定」です。そこにあるのは目的・方針・社会的意義。
デザイナーはそれらを視覚・言葉・体験へ翻訳する立場にあります。
もし経営の言葉を理解せずにデザインを始めれば、伝わりが弱くなります。
つまり、グランドマップを理解するとは、経営とデザインを同じ言語でつなぐことなのです。
2. 意匠ではなく“構造”をデザインするため
グランドマップを知ることで、デザインの対象が「見た目」から「構造」へと広がります。
- 環境を知る=市場やユーザーの動線を読む(情報設計・UX)
- 強みを知る=差別化の根拠を見せる(CI/VI・ブランド資産)
- 意思を知る=判断基準を明確にする(やらないデザインを決める)
- 志を知る=物語と共感をつくる(コピー・ビジュアル)
- ポジションを知る=競合との距離をデザインする(トーン&マナー)
これらを理解することで、表層ではなく“意味の構造”をつくることができます。
3. 「経営の再現者」ではなく「共創者」になれる
グランドマップを共有しているデザイナーは、単なる発注対応者ではなく、経営とともに未来を描く“共創者”になれます。
経営者が「こういう未来をつくりたい」と語るとき、その思いを体験へと翻訳し、顧客に届く形にするのがデザインの役割です。
つまり、グランドマップを理解するとは、デザインが経営の一部として機能し、企業の意思決定に並走できる力を得ることなのです。
4. 判断と一貫性が生まれる
ブランディングの現場では、毎日のように「どの方向が正しいか」を判断する必要があります。
グランドマップを共有していれば、意見の対立が起きても「志」や「意思」を基準に戻れる。
その結果、広告・Web・店舗・パッケージなど、あらゆる接点でトーンが揃い、ブランドとしての整合性が生まれます。
グランドマップをデザイナーのヒアリングに活かす視点!
経営者や担当者に「どんなデザインを希望されていますか?」と聞いていませんか?
――実は、それはあまり良い質問ではありません。
なぜなら、その質問に対する答えの多くは「表層的な見た目」にとどまるからです。
「明るくしたい」「高級感を出したい」「若者向けにしたい」など、これらはすべて“表現の希望”であって、そもそも“経営の課題”ではありません。
デザイナーが本当に理解すべきは「何を解決したいのか」「どこへ向かいたいのか」という背景の構造です。
ですからデザイナーが行うべきヒアリングは、見た目の要望ではなく、グランドマップの5要素(環境・強み・意思・志・ポジション)を掘り出すことにあります。
たとえば、こんな質問が鍵になります。
■ 環境(外の現実を見据える)
- この業界は今、どんな変化の中にありますか?
- 顧客の購買行動や価値観はどう変わってきていますか?
- 外部環境でチャンスだと思うこと、逆に脅威だと感じることは?
■ 強み(内の資源を見極める)
- 他社にない、自社ならではの技術・文化・人・仕組みは?
- 顧客が「ここが好き」と言ってくれるポイントは?
- その強みを裏付ける具体的なエピソードは?
■ 意思(戦略的方向を決める)
- 会社として「何をやらない」と決めていることはありますか?
- この先3〜5年で“こうなっていたい”という姿は?
- デザインを通じてどんな行動変化を生みたいですか?
■ 志(存在理由を定義する)
- この事業を通じて、社会にどんな価値を残したいですか?
- 自分たちは“誰のどんな未来”をよくしたいと思っていますか?
- 一言で言うなら、会社の“約束”は何ですか?
■ ポジション(社会の中での立ち位置を宣言する)
- 業界の中で、自分たちはどんな立場・役割を果たしたいですか?
- お客さまや社会から“どんな存在”として見られたいですか?
- 例えるなら、どんな企業やブランドに近いですか?
■ ゴール(未来像を可視化する)
- いつまでに、何を実現できていれば理想ですか?
- 成果をどう測りますか?(数字/行動/認知など)
- そのゴールに向けて、何が一番の障壁になっていますか?
特にデザイナーが抑えるべき3つの要素
1. 強み → ビジュアル・トーンの根拠(CI/VI設計)
「強み」は、デザインを支える“根拠”です。たとえばブランドマネジメント力、直営力、職人技など──その企業だけが持つ資源を言語化できれば、トーンや色、素材、写真の質感といった視覚的要素に一貫した理由を与えられます。デザインは好みで決めるものではなく、「この強みをどう見える形にするか」という翻訳作業なのです。
2. 意思 → やらないことを決める(ガイドライン策定)
「意思」は、デザインにおける判断の基準です。経営が何を優先し、何をしないのかを明確にすることで、デザインのブレを防ぎます。「短期的な話題性よりも長期的な信頼を優先する」「流行フォントは使わない」「割引訴求はしない」──こうした“やらないことリスト”こそが、ブランドを守る最強のデザインガイドラインです。
3. 志 → ブランドストーリー・コピー・ビジョンページ
「志」は、企業の社会的な約束であり、ブランドの物語そのものです。デザインの役割は、その志を言葉と体験で語ること。
コピーライティング、タグライン、ビジョンページ、キービジュアル──すべては志を代弁する表現です。志が明確なブランドは、ユーザーに共感と信頼を生み、時間を超えて記憶に残る。つまり、志はデザインに“魂”を与える要素なのです。
まとめ:グランドマップの先にあることは?
改めて、グランドマップは、経営を定性的に整理するための中期経営計画における「定性的目標」です。
まず「環境・強み・意思」を踏まえて、自社がどんな価値を社会に提供したいのかという志を定めます。
志が定まることで、企業の存在理由が明確になり、その延長線上でポジション(どんな立ち位置で価値を届けるか)とゴール(どんな未来を実現するか)が具体化されていきます。
ここでいうゴールとは、短期の売上や数値目標ではなく、長期的な文化的成果を目指すものです。
デザインはそのために、“未来の評価軸”を見据えながら普遍性と独自性を両立させる表現をつくることが求められます。
中川政七商店が掲げる「各地に“産地の一番星”を生み、100年後に『工芸大国・日本』と言われる」というビジョンは、その象徴的な例です。
そしてグランドマップは「定性シート」として理念や方向性を固めつつ、必ず「定量シート」へと接続されます。
定性シートが描くのは、“何を・なぜ・どんな意志で”行うか。
定量シートが示すのは、“いつまでに・どれくらい・どんな指標で”実現するか。
つまり、グランドマップは理念(抽象)と実行(具体)をつなぐ中継点なのです。
デザイナーにとっても、ここを理解しておくことで、単なる表現制作を超え、経営戦略を実現するデザインを提案できるようになります。
デザインを“数字とつながる言葉”にするために、まずこの定性の地図=グランドマップを描くことが、すべての出発点なのです。