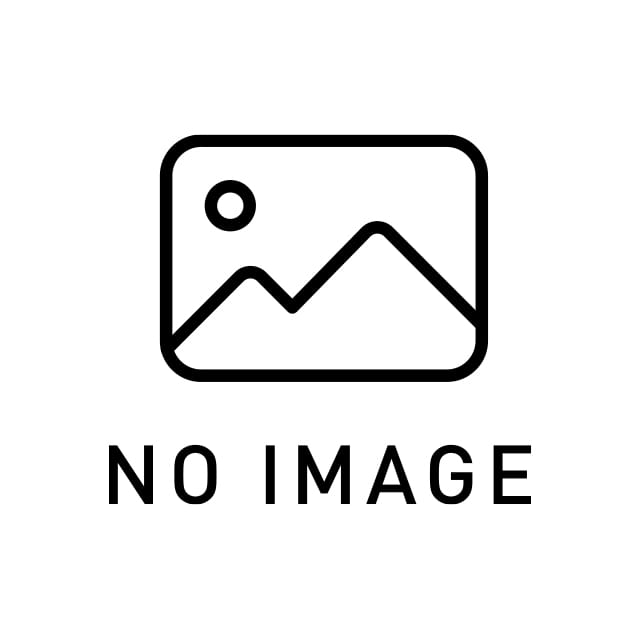【マルチタスクはNG?】同時に15案件を回すディレクション術・仕事術を紹介

「〇〇さんってどうやって同時に15案件も回してるの?私なら絶対に頭が爆発する…」 「締切に追われながらでもいつも冷静で、全部のプロジェクトをきちんと管理できるなんて」
こんな言葉をよく同僚からかけられます。でも実は、私も初めから上手くできていたわけじゃありません。数年前は案件が5つを超えただけでパニック状態になってました。そして毎晩遅くまで地獄のような残業。。。それでも追いつかず、精神的にも肉体的にも限界を感じていたのです。
目次
複数プロジェクト管理の課題とは、「脳のオーバーヒート」が原因?
Webディレクターとして7年以上、数えきれないほどのプロジェクトを担当してきて痛感するのは、僕たちの限界は多くの場合「時間」ではなく「脳の処理能力」だということ。
Webディレクターの仕事は本質的にマルチタスク。クライアントとの打ち合わせ、デザイナーやエンジニアとのコミュニケーション、スケジュール管理、品質チェック、予算管理…一人でこなす役割があまりにも多すぎるんです。
例えばこんな日もあります・・・。5つの異なるクライアントとの直打ち合わせ(初回ミーティングやクライアンへのデザイン提案など)を抱え、さらに急ぎの社内デザインチェックが3件、クライアントからのメール返信10件ほど。
これだけやると、「脳のオーバーヒート」につながります。特に前頭前皮質の背外側部(dlPFC)という部位は、計画立案や意思決定を司る重要な領域。この部分が常に高負荷状態になると、判断力が鈍り、ミスが増え、創造性も低下してしまうんです。
作業が追いつかなくなると人は残業をしはじます。そしてどれだけ時間を増やしても、脳が疲弊します。(僕はある時期、毎日夜遅くまで残業し、休日も仕事をする生活を送っていました。確かに作業時間は増えましたが、判断ミスやコミュニケーション不足による手戻りも増え、結果的に効率は下がっていたんです。)
それでは良いアウトプットは得られません。
ここで大切なのは「脳の状態」を最優先に考えた働き方をすること。なぜなら脳を効率的に使わなくては良い仕事などはできていないからです。
「処理モード別」タスク管理で脳の負荷を軽減する
私が実践している方法は「処理モード別」のタスク管理。
単に時間を区切るだけではなく、タスクの性質に合わせて脳の使い方を意識的に変えるのです。
【高集中モード】深い思考が必要な案件の作業
朝が正直、一番の頭がクリアな状態になります。ですからそのタイミングで、サイト設計や提案書作成など、複雑かつクリエイティブな思考を要する仕事に取り組みます。
私の場合、午前9時から11時が最も頭が冴えている時間帯。この時間帯には外部からの干渉を一切シャットアウトします。メール通知はオフ、社内チャットは見れない状態、電話は取らない!
じまbんbn先日、大手製造メーカーのWebサイトのコンセプ設計をしているときに、この「高集中モード」で取り組みました。90分間の深い集中の結果、クライアントに驚かれるほど的確な提案ができました。「こちらの考えを読んでいるようだ」と言われたときは、この時間の使い方が間違っていないと確信しました。
【流し処理モード】単純作業やルーチン業務
昼食後の13時から14時半頃は、どうしても脳が少しぼんやりしがち。この時間帯には創造的な思考よりも、決まりきった作業や定型的な連絡、データ整理などの「流し処理」にあてます。
メール返信、進捗管理表の更新、簡単な資料修正など、ある程度「自動操縦」でこなせる仕事をまとめて片付けます。この時間帯に25分集中して5分休憩するポモドーロテクニックを使うと、集中力が持続しやすくなります。
【同時進行モード】マルチタスクを賢く活用
すべてのタスクで集中力を分散させるのはNG。でも、脳の干渉が少ない組み合わせのタスクなら、同時に進めることもできます。
例えば、情報収集目的のオンライン会議を聞きながら簡単な資料確認をするといった具合に。
先日のチームミーティング中、僕は話を聞きながら簡単なスケジュール調整を行いながら会議の内容も把握できました。
ただし、これはあくまで片方が自動的にできるレベルのタスク同士の組み合わせに限ります。
両方とも思考を要するタスクの同時進行は避けるべきです。
私の1日の実践例
- AM 9:00〜10:30(高集中モード) → 新規プロジェクトの設計、重要な提案書作成
- 10:30〜11:00(同時進行モード) → 定例MTGに参加しながら簡単なタスク整理
- 11:00〜12:00(高集中モード) → クライアントフィードバックの反映、修正方針決定
- 13:00〜14:30(流し処理モード) → メール返信、簡単な資料修正、進捗管理表更新
- 15:00〜16:30(高集中モード) → デザイン確認、修正指示、課題解決の意思決定
- 16:30〜17:30(同時進行モード) → チームMTGに参加しながら軽いタスク処理
- 17:30〜18:00(流し処理モード) → 明日の準備と残タスク整理
認知オーバーフローを防ぐための「脳キャッシュ」の活用
15案件も抱えていると、記憶だけに頼るのは限界があります。私たちの脳の作業記憶(ワーキングメモリ)は驚くほど少ない情報しか同時に保持できないんです。
そこで僕は「脳キャッシュ」という考え方を取り入れています。
これは言ってみれば、脳の外に一時的な記憶装置を作るようなもの。私の場合はNotionを使って、各プロジェクトごとで覚えておく内容を整理しています。
例えば、あるAサイト改修作業中に、Bの化粧品メーカーの案件について良いアイデアが浮かんだとします。以前の私なら「後で思い出そう」と思って結局忘れてしまうか、そのアイデアが気になって目の前の作業に集中できなくなっていました。
ここで「脳キャッシュ」という考えの登場です。つまりアイデアが浮かんだらすぐにNotionの該当プロジェクトページにメモするわけです。
「このアイデアを記録した」という安心感が生まれ、目の前の作業に再び集中できるようになりますし、大切なアイデアも忘れずにしっかりと別のアイデアへと応用もできます。
「スイッチングコスト」は高くつく、タスク間の「脳のリセット」が15案件を回す鍵
タスクを切り替えるたびに私たちの脳はエネルギーを消費します。これが「スイッチングコスト」と呼ばれるもの。一日中このコストを払い続けると、夕方には完全に脳が疲弊してしまいます。
そこで私は、タスクの切り替え時に30秒から2分程度の「脳リセット」時間を設けています。特に重要な企画書作成から別のサイト設計に移るような、高負荷から高負荷への切り替え時には必ず実施します。
- 立ち上がって窓の外を眺める
- 目を閉じて3回深呼吸する
- 肩を回して体をほぐす
- 水を一杯飲む
- ちょっと横になって目をつぶる(在宅ワークの場合はできる) などなど
めちゃくちゃ些細なことですが、これが脳の状態をリセットし、次のタスクへの移行をスムーズにしてくれるんです。
先日も、朝の高集中作業から11時の社外ミーティングへの切り替え時に、この「脳リセット」(=リビングで横になって目をつぶる)を行ったおかげで、頭がクリアになり、ミーティングでも的確な判断ができました。
定期的な「リフレクション」で全体を俯瞰する習慣
15案件も同時に進めていると、どうしても「木を見て森を見ず」の状態になりがちです。個々のタスクに集中するあまり、全体の優先順位や関連性を見失ってしまうんです。
そこで私は、毎日終業前の15分間と週末の金曜日午後を「リフレクション(振り返り)」の時間に充てています。
毎日の終業前には、その日の成果を確認し、明日取り組むべき最優先の3つのタスクを決めます。これにより、翌朝すぐに集中して作業に取りかかれます。
金曜日の午後(僕の場合は16時から17時)は、すべてのプロジェクトの状況を俯瞰します。
- 遅れが生じているもの
- 次週重点的に取り組むべきもの
- 潜在的なリスクがあるものをチェック
週末明けからスムーズに動き出せるよう準備します。
先月、この習慣のおかげで週明け、クライアントからの特急リクエスト(よくきます・・・)にも慌てずに対応できました。金曜日の振り返りで全体の進捗状況を把握していたからこそ、どのタスクを調整すれば対応可能かがすぐにわかったんです。
【実践編】こんな感じでやってます。
1.特定のクライアントの作業を集中してやる
僕がやっているのは可能な限り特定のクライアントとのやり取りを特定の曜日に集中させています。Aクライアント(化粧品メーカー)は月曜日と水曜日、Bクライアント(不動産会社)は火曜日、Cクライアント(ECサイト運営)は木曜日というように決めておくと、「今日はAクライアントについて深く考える日」「今日はA社のことだけ考える」と脳に伝えることができ、関連タスクをまとめて処理できます。
ちなみに曜日配分としては、認知負荷の高い大型プロジェクトと比較的シンプルな小規模案件を組み合わせるようにしています。常に高負荷の案件ばかりだと脳が疲弊してしまうので、「息抜き」になるような案件も並行して進めるのが理想的です。
2.タスクをタイプごとに分けて対応する
さらに、タスクのタイプ別に日を分けることも効果的です。月曜日と木曜日はデザイン確認に集中し、火曜日と金曜日はコーディング系のチェックを行うといった具合です。似た種類のタスクをまとめることで、脳の切り替えコストを大幅に減らせます。
また1日の中に割り込み対応の時間をあらかじめ確保しています。予定外の要求は必ず発生するもの。私の場合は14時から15時を「バッファタイム」として確保し、急な依頼やトラブル対応に充てています。
まとめ:15案件並行管理から学んだ「脳と共存する働き方」
最初に15案件を同時に任されたとき、正直「無理かも」と思いました。でも脳科学的なアプローチを取り入れたことで、今では無理なくこなせるようになっています。
処理モード別に時間を区分することで脳の負荷を最小化し、脳外キャッシュで作業メモリを解放し、タスク間リセットで脳波を整え、定期的なリフレクションで効率と質を維持する。
これらの方法は、単に仕事のパフォーマンスを上げるだけでなく、私の生活の質も大きく向上させてくれました。残業が減り、休日は趣味に没頭できるようになり、精神的にも余裕が生まれたんです。
「仕事のできる人」と言われるのは嬉しいですが、私が本当に目指しているのは「脳と上手に付き合いながら、持続可能な形で成果を出し続けられる人」。これからも脳科学の知見を取り入れながら、効率的なプロジェクト管理の方法を模索し続けたいと思います。
みなさんも、ぜひ自分の「脳の使い方」を見直してみてください。きっと新しい可能性が見えてくるはずです。