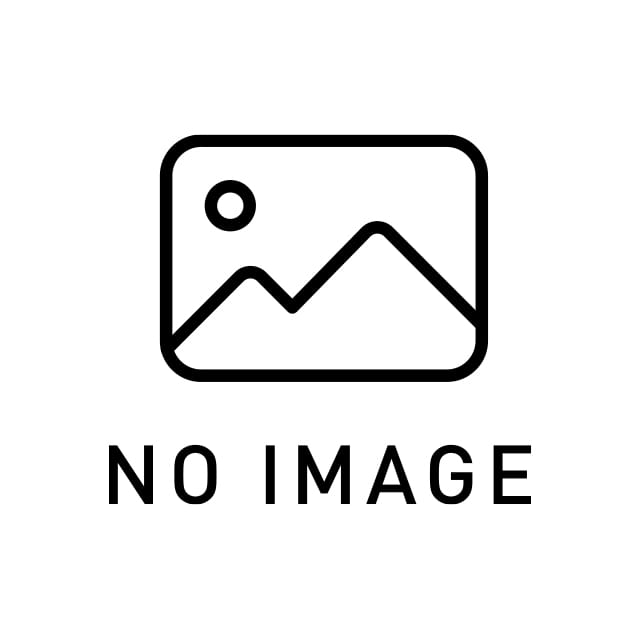【超実践編】デザイン思考はこう使え←明日から使える事例あり

デザイン思考は、クリエイティブの分野だけでなく、多くの業界や分野でよく耳にする言葉です。
でも「デザイン思考という概念を学んだとて、仕事の役に立つの?」というのが本音。
だから今回はデザイン思考を身の回りの仕事や出来事に応用してみることもやってます。
デザイン思考は難しく考えなくて良くて、実践的に使える「思考アプローチ」だと思ってほしいです。ちょっとした問題解決やアイデア探しにも役立ちます。
目次
デザイン思考とは一体何か??
じゃあそもそもデザイン思考ってなにか?というと、ユーザー中心の視点でイノベーションを創出するための思考法で、複雑な問題を解決するための問題解決のアプローチです。具体的にはユーザーのニーズや課題を深く理解し、共感することから始まり、そこからアイデアを生み出し、プロトタイピングと検証を繰り返しながら、解決を導き出していきます。
・・・とこのように言われると難しく思えるかもしれません。でもデザイン思考はとにかく、誰でも、そしてどこでも使える身近な思考アプローチである、ここをちゃんと覚えてほしいです。つまりデザイン思考は難しい理論や方法論ではなく、実践的に使える「思考アプローチ」ということ。
デザイン思考5つのシンプルなステップで構成されています。
- 共感: 問題を抱えている人のニーズや感情を理解する
- 問題定義: 解決すべき課題を明確にする
- アイデア発想: 自由な発想で解決策を考え出す
- プロトタイピング: アイデアを形にする
- テスト: ユーザーに試してもらい、フィードバックを得る
こうしたステップを通じて、問題の表面的な原因ではなく、本質的な原因を捉えにいきます。そしてデザイン思考で大切なのは、完璧な解決策を目指すのではなく、試行錯誤を通じてより良い解決策に近づいていくという考え方です。
問題解決よりも人間中心の視点から問題の本質理解が大事!
デザイン思考を問題解決をする思考ツールと考えている人もいるかもしれません。
それはそれで正しいのですが、僕はむしろデザイン思考の本義とは、問題そのものを深く理解することだと考えています。
デザイン思考は、5つのプロセスがあるわけですが問題解決のプロセスに入る前の、「共感」と「問題定義」に十分な時間をかけて行くべきだと思っています。
なぜなら今見えている問題とは表面的な部分であることが多く、それをデザイン思考を使用することによって、人間中心の視点から問題を深く掘り下げて、その理解に基づいたアイデア創出が可能になるからです。
実際、「共感」と「問題定義」ではいろんな角度から問題を探求し、課題の種(可能性も含めて)をたくさん探し出します。その種をアイデア創出の前から知っておくことで、クリエイティブの土台となって今の問題をちゃんと理解することにつながります。そこから生まれる解決策は、単なる一時的な対処ではなく、新しい価値を生み出すものとなるでしょう。
共感→問題定義で大切なのは「なぜ?」の問いかけ
デザイン思考の「共感」と「問題定義」ステップは、とにかく問題の本質を多角的に理解することが大切。この段階では、様々な角度から問題を探求し、課題の種を見つけ出すことが求められます。
この段階で大切なのは「なぜ?」を繰り返し問いかけること。なぜなら問題の根源に迫ることができるからです。例えば、「ユーザーがこの製品を使いにくいと感じるのはなぜか?」という問いから始まり、「機能が複雑だから」「説明書が分かりにくいから」「ユーザーのスキルレベルに合っていないから」など、様々な仮説を立てることができます。さらに、「なぜ機能が複雑なのか?」「なぜ説明書が分かりにくいのか?」と掘り下げることで、問題の本質により近づくことができるのです。
これらの過程では正解を導き出すよりも、とにかく探求こそがゴールです。この段階を深く考えていくことで、アイデア創出やプロトタイピング、テストのステップへと進むことで、真に効果的で持続可能な解決策を生み出すことができるのです。
こんな身近な課題が、デザイン思考で解決できそう!
仕事
- 仕事が効率化できない: タスク管理やツールの活用、仕事の仕方の改善など
- 人間関係がうまくいかない: コミュニケーション方法の工夫、相互理解を深めるなど
- 新しいアイデアが浮かばない: 発想方法の改善、情報収集や刺激を受けるなど
- プレゼンテーションがうまくできない: 構成や資料の見直し、練習など
- 仕事とプライベートのバランスが悪い: 時間の使い方を見直し、優先順位を考えるなど
日常生活
- 朝の準備がスムーズにできない: 時間管理や動線の改善、必要な物の整理など
- 家事の負担が大きい: 家事分担や効率化、便利なツールの活用など
- 家族間のコミュニケーション不足: コミュニケーション方法の工夫、共通の趣味を見つけるなど
- 買い物が面倒: ネットショッピングの活用、配達サービスの利用など
- 趣味や娯楽の時間が少ない: 時間の使い方を見直し、効率的な活動方法を考えるなど
身近に使おうデザイン思考的アプローチ【悩み解決編】
私はWebディレクターとして多くのデザイナーや顧客と関わっていますが、デザイン思考を効果的に使いこなしている例はまだまだ少ないのが現状です。
つまりデザイン思考という言葉自体の認知にくらべて、実際面=それを活用できる・活用している企業はそれほど多くありません。
冒頭に伝えたようにデザイン思考は、ただ製品開発やサービスデザインに限らず、日常の仕事や生活の中でもちゃんと役立つ思考ツールです。
ここでは紹介する5つの場面でデザイン思考を使うことで、より良い解決策を見出すことができるでしょう。
デザイン思考の仕事編【実践編】
1.アイデアが浮かばないときの打開策
仕事で企画書を書かなきゃいけないのに、アイデアが全く浮かばない…!そんな経験ありませんか?そんなときこそ、デザイン思考が役立ちます。
アイデアが浮かばない原因は、企画の対象となるユーザーや顧客の立場に立って考えられていないからかもしれません。机に向かってひたすら考えを巡らせても答えにたどり着けないのであれば、実際にユーザーと接点を持ち、その日常や悩み、期待などに寄り添ってみるといいでしょう。具体的には、インタビューやフィールドワークを通じて、ユーザーの生の声を聞くことが有効です。例えば、新しいモバイルアプリのアイデアを考える際、対象となるユーザー層にインタビューを行い、日常生活での不便な点や、既存のアプリに対する不満などを聞き出します。また、身近にいる友人や家族から意見を聞くのも良い方法です。(共感)
ユーザーの声から見えてきた課題を整理し、明確化します。大切なのは表面的な問題ではなく、その奥にある本質的な問題は何かを見極めることです。例えば、「商品の認知度が低い」という問題の背景には、「商品の価値が伝わっていない」というより根本的な課題があるかもしれません。この段階で、問題をより深く掘り下げることで、的確なアイデア創出につなげることができます。(問題定義)
定義された問題に対して、可能な限り多くのアイデアを出すことが重要です。ブレインストーミングやマインドマッピングなどの手法を用いて、自由な発想を促進します。アイデアの質よりも量を重視し、斬新で大胆な発想を歓迎します。例えば、「商品の価値が伝わっていない」という問題に対して、「商品の使用シーンを動画で紹介する」「インフルエンサーとのコラボレーション」「ポップアップストアの開催」など、様々なアプローチを考えます。(アイデア創出)
出されたアイデアの中から実現可能性の高いものを選び、試験的に実践します。例えば、「商品の使用シーンを動画で紹介する」というアイデアであれば、簡単な動画を作成し、一部のユーザーに視聴してもらいフィードバックを得ます。この段階で、アイデアの有効性や改善点を明らかにすることができます。(プロトタイピング)
2.デザインスキルが伸び悩んでいる
自分自身をユーザーとして捉え、客観的に観察することから始めます。どのスキルが伸び悩んでいるのか、そのために感じている不安や悩みを明確にします。具体的にはどのようなデザインスキルが不足しているか。例えば、配色、レイアウト、タイポグラフィ、ユーザー体験design (UX) など、様々な領域が考えられます。それによってどのような不安や悩みを抱えているのかを明確にし、自分の強みや弱み、学習スタイルについても振り返ります。(共感)
次にデザインスキルが伸び悩んでいる原因を特定するステップです。単に「才能が足りない」「努力が足りない」といった表面的な理由ではなく、根本的な問題を見極めることが求められます。例えば、デザイン理論の理解が不十分、適切なフィードバックが得られていない、実践的な経験が少ない、新しいデザイントレンドへの知識が追いついていない、などが考えられます。問題を明確に定義することで、解決へのヒントが得られます。(問題定義)
特定した問題を解決するためのアイデアを自由に発想します。既存のデザイン学習方法にとらわれず、幅広い視点からアプローチを検討します。オンラインのデザインコースの受講、デザインコミュニティへの参加、メンターの発掘、実践的なプロジェクトへの取り組み、他分野(心理学、マーケティングなど)の学習による視野拡大など、多様な手法を考えます。アイデアの数を重視し、斬新な発想を歓迎します。(アイデア創出)
出されたアイデアの中から、実行可能性とインパクトの大きさを基準に選択し、試験的に実践します。例えば、1ヶ月間、毎日1時間のデザイン演習に取り組む、オンラインのデザインコミュニティに積極的に参加し、フィードバックを得る、新しいデザインソフトウェアを使って実験的な作品を制作する、などが考えられます。小さく始めることで、習慣化の難易度や効果を検証し、アイデアの実現可能性や改善点を明らかにします。(プロトタイピング)
プロトタイプの結果を評価し、スキル向上の度合いを確認します。うまくいった方法は継続し、改善の余地があるものは修正します。この過程で得られた気づきを次のサイクルに活かし、よりパーソナライズされた学習方法を確立していきます。(テスト)
3.AIチームでAI導入を進めることに・・・
例えばあなたがAIチームのリーダーとして、社内の様々なステークホルダーを巻き込みながら、AIを導入していかなければならないとします。社内でAI活用を促進するために、デザイン思考の5つのステップを適用してみましょう。
まずは、社内の各部署の業務内容や課題を深く理解することから始めます。AIを活用することで、どのような業務が効率化できるのか、どのような価値が生み出せるのかを、現場の視点で把握します。同時に、AIに対する社員の意識や懸念点も汲み取ります。(共感)
収集した情報を整理し、AI活用の阻害要因を明確にします。例えば、AIに対する知識不足、既存業務とのマッチング難しさ、導入コストへの懸念など、様々な課題が浮かび上がるはずです。これらを整理し、優先的に取り組むべき問題を特定します。(問題定義)
問題解決のためのアイデアを出し合います。AIチームだけでなく、他部署の社員も巻き込んで、AI活用のアイデアを募ります。例えば、AIを活用した業務改善提案制度の創設、社内向けAIセミナーの開催、AIツールの試験導入など、多様な施策を検討します。(アイデア創出)
出されたアイデアの中から、実現可能性が高く、インパクトの大きいものを選び、試験的に実施します。例えば、特定の部署で、AIを活用した業務改善プロジェクトを立ち上げる、といった具合です。小さく始めることで、効果を検証し、改善点を洗い出します。(プロトタイピング)
プロトタイプの結果を評価し、AI活用の効果や社員の反応を確認します。成功事例は社内で共有し、AIへの理解を深めます。課題が見つかった場合は、フィードバックを元に改善策を講じます。このサイクルを繰り返すことで、AI活用の輪を社内に広げていきます。(テスト)
ここで重要になってくるのは、社員一人一人の声に耳を傾け、その懸念や期待を理解しようとすること、そして、全社的な協力体制を構築することです。
AIチームのリーダーは、社員の多様な視点を生かし、導入に向けた検討過程を通じて、社員と創造的な導入方法を見出していき、AIと人間が「協働する新しい働き方」を考えていくことが求められます。
そうすると「一緒に考えてきた」という関係で、より社内導入がスムーズにいくことにもつながります。だからこそ、トップダウンの一方的な指示ではなく、社員の主体性を尊重し、対話を重ねることが肝要です。
4.社内会議にデザイン思考を活用する
もっとも初歩的なデザイン思考活用の場面としては、日々の社内会議です。僕は社内会議のほとんどが生産的な議論をできていないと思っています。だからデザイン思考を取り入れることで、より創造的な議論につなげると思います。
会議に参加するメンバーの立場に立って、それぞれの関心事や課題を理解します。事前にアンケートを取ったり、個別に話を聞いたりすることで、参加者の本音を掴みます。(共感)
共感の段階で得られた情報を整理し、会議で解決すべき核心的な問題を明確にします。単に議題を設定するのではなく、参加者の真のニーズに基づいて、会議の目的を再定義します。(問題定義)
問題解決のためのアイデアを自由に出し合います。ブレインストーミングなどの手法を用いて、既存の枠組みにとらわれない斬新な提案を引き出します。批判は禁止し、量を重視します。(アイデア創出)
出されたアイデアを具体的な行動プランや議事録の形で可視化します。会議の進行方法や決定事項を、参加者が理解しやすい形で示すことが重要です。(プロトタイピング )
プロトタイプに基づいて会議を実施し、参加者の反応を観察します。会議後には、振り返りを行い、改善点を洗い出します。次回の会議に向けて、プロトタイプを修正していきます。(テスト)
デザイン思考のプライベート編【実践編】
プライベートにも解決できない悩みがたくさんあると思います。そんなときにこそ、マインドセットとしてデザイン思考を覚えておくだけでも非常に便利です。
ここではプライベートでデザイン思考を使う事例をいくつか例としてあげてみます。
01.子育てが上手くいかない・・・
デザイン思考を活用して、「自分自身が親の場合、子育てが上手くいかない」という問題を解決していく方法を考えてみます。自分自身の状況に向き合い、内省しながら、クリエイティブに解決策を見出していくプロセスが重要です。
まずは、自分自身の感情や思考、行動パターンを客観的に観察し、理解を深めます。子育てのどの部分で困っているのか、具体的な場面や状況を思い出してみましょう。子供との接し方に自信が持てない、感情的になってしまう、一貫性のある態度で接することが難しいなど、自分の弱みや課題を明確にします。例えば自分自身の価値観や信念が、子育てにどのように影響しているかを観察してみるのもいいです。子供に対して完璧を求めすぎていないか、自分の期待を無意識に押し付けていないかなど、自分の態度や言動を振り返ってみましょう。また、子供の個性や興味・関心に耳を傾け、子供の視点に立って物事を見ることの大切さを再認識します。(共感)
次に子育ての困難さの根本的な原因を特定します。単に子供の行動の問題と捉えるのではなく、自分自身のストレス対処法、子供とのコミュニケーションの取り方、育児知識の不足など、複合的な要因が考えられるので、それらとちゃんと向き合って見極めていきます。また、自分自身の価値観や期待が子育てに与える影響の中で、問題となっている点を明確にします。例えば、「子供の自主性を尊重できていない」「自分の期待が子供の負担になっている」「子供の多様性を受け入れられていない」などの課題が浮かび上がるかもしれません。これらの問題の根底にある自分の価値観や思い込みを特定することが重要です。(問題定義)
続いて特定した問題に対する具体的なアプローチを考えてみます。例えば、自分自身のストレス管理方法の見直し(運動、趣味の時間の確保など)やパートナーや周囲の人々との協力体制の強化(役割分担、サポートの要請など)があります。また自分の価値観を再定義するなら、自分の価値観や期待をオープンに子供と話し合い子供の意見に耳を傾けたり、多様な生き方や価値観を認める柔軟性を身につけたり、完璧主義から脱却し、子供の失敗や挑戦を温かく見守る姿勢を培うなども考えられます。(アイデア創出)
アイデアの中から実行可能なものを選び、試験的に実践します。例えば、「子供の興味・関心を尊重する」というアプローチであれば、子供の好きな活動を一緒に探求したり、子供の意見を取り入れた家族の意思決定を試みたりします。その際、自分の価値観を一旦脇に置き、子供の視点に立つことを意識します。
プロトタイピングの結果を評価し、アプローチの有効性を確認します。子供の反応や自分自身の心境の変化に注目し、価値観の再定義が子育てに与えるポジティブな影響を観察します。うまくいった部分は継続し、さらなる改善点があれば修正します。この過程で得られた学びを次のサイクルに活かし、より柔軟で子供の個性を尊重した子育てを目指します。
02.キャリアの選択と成長
デザイン思考を活用することで、
目標は自己理解を深め、様々な可能性を探求し、試行錯誤を重ねながら、自分らしいキャリアを設計し
まずは自分自身の感情、強み、価値観、情熱などを詳細に観察し、理解を深めます。これまでのキャリアの中で、充実感を感じた経験、ストレスを感じた経験を振り返ります。また、自分の理想のライフスタイルや将来のビジョンについても考えてみましょう。自分自身を多角的に理解することが、キャリアデザインの第一歩です。(共感)
キャリアの選択と成長における問題点や課題を明確にします。現在のキャリアに満足していない理由、スキルアップの必要性、ワークライフバランスの問題など、根本的な課題を特定します。また、自分の強みや情熱が十分に活かされていない点にも着目しましょう。問題をクリアに定義することで、解決の方向性が見えてきます。(問題定義)
アイデア創出の段階では、問題解決のためのアイデアを自由に発想します。一つの方向性として、自分の強みや情熱を活かせる新しい職種やポジションを探求することが考えられます。自分の能力を最大限に発揮し、やりがいを感じられるキャリアパスを見出すことができるかもしれません。またスキルアップのための資格取得や研修への参加も有効なアプローチです。新しい知識やスキルを習得することで、キャリアの選択肢を広げ、価値提供の幅を拡大することができます。その他に、メンターや支援者を見つけ、キャリアについてアドバイスを求めることもあります。経験豊富な先輩や専門家から客観的な視点やガイダンスを得ることで、自分の強みや可能性を再認識し、キャリアの方向性を明確にすることができます。(アイデア創出)
アイデアの中から実行可能なものを選び、試験的に実践します。例えば、「新しい職種の探求」であれば、興味のある業界の人々にインタビューしたり、関連するセミナーに参加したりして、実際の仕事内容や必要なスキルを理解します。また、小さなプロジェクトを通じて、その職種で求められる能力を体験的に学ぶことも有効です。(プロトタイピング)
プロトタイピングの結果を評価し、アプローチの有効性を確認します。新しい職種について理解が深まったか、必要なスキルが明確になったか、自分の強みや情熱との適合性が高いかなどを多角的に評価します。フィードバックを基に、アプローチを改善し、より自分に合ったキャリアパスを模索していきます。(テスト)
つまり、デザイン思考は、「試行錯誤」を続けるってことが大切
時代はどんどん変わっていくので、組織も、製品・サービスも生まれ変わる必要があります。
そして、そのためには一人一人が「試行錯誤」を続ける必要があります。
時代の変化に合わせて進化を続ける企業になるには、組織としていかに「試行錯誤」ができるか、個々人が自律的に創造性を発揮できるかが問われます。
その際に大切になってくるのがデザイン思考です。